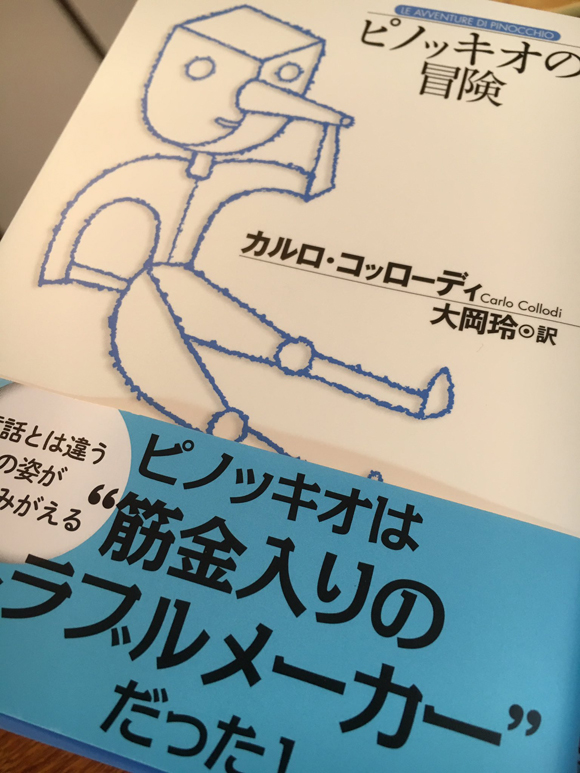大岡玲さんの新刊『ピノッキオの冒険』(光文社古典新訳文庫)が出た。
巻末の長文書き下ろし解説60ページの中で触れられている通り、そもそも大岡さんは角川文庫版の『新訳 ピノッキオの冒険』に始まり、前著『たすけて、おとうさん』、『不屈に生きる 名作文学講義 本と深い仲になってみよう』と、ここ10数年一貫してピノッキオにまとわりつかれてきた。今回の新訳版で、ピノッキオしばし打ち止めということのようだ。
前二作の大岡さんがあまりにもピノッキオに熱かったので、ふうんそうなのか、じゃあそのうちに正調ピノッキオの冒険譚を読んでみようかなと、例によってディズニーのそれしか知らないわたしは思っていた。とはいえディズニーは基本的にぜんぶ大嫌いなので、いくら本物のピノッキオはディズニーとは全然違うんですと大岡さんに説かれても、読むか読まないか怪しかった。
それで今回の新訳本が出ても、じつは巻末の解説だけ読んで、本文は積んどくにするつもりだったが、ちょうど昨日、『フライの雑誌』次号110号の入稿が終わったばかりで、そのまま「本物のピノッキオの冒険」に巻き込まれてみた。
いやー、ピノッキオ腹立った。腹立ちすぎて一気に読んでしまった。そしてちょうど似たような年頃の子どもを持つ父親として、ピノッキオの「おとうさん」であるジェッペットさんのご苦労が、本当に身にしみた。
ジェッペットさんてば、ほんの気まぐれで、木の棒から喋る人形を作ってしまったばかりに、友だちからは思いきり殴られるわ、上着は失くすわ、当の息子からは何回も何回も裏切られるわ、海で難破するわ、あげく全長1kmの巨大サメの腹の中で何年も暮らして、ひげも頭の毛も真っ白になるわ、災難続きもいいところだ。ピノッキオさえ作っていなければ、穏やかな一人暮らしの日々を愉しめていただろうに。釣りでもしながら。
ピノッキオといえば、子どもとはそもそもそういう生きものなんだろうけれども、それにしても馬鹿すぎる。こんな馬鹿息子はとっとと揚げ物にでもロバにでもなってしまえと思ったが、でも、まあ、そこは結局親子の人情で、ABCノートが欲しいと言われればなんとかしてあげたいし、人生における果物の皮と芯の大切さも教えてあげたい、というジェッペットさんの気持ちは分かりすぎるくらい分かる。
わたしは『ピノッキオの冒険』の最後のシーンで、これからますます見通しが悪くなるだろう世の中を生きるにあたり、本人が望むと望まないとにかかわらず、多かれ少なかれ運命というジェットコースターに振り回されるはずの、うちの子どもの先行きと、いろいろ思い通りにならない我が身と、19世紀末のイタリア・トスカーナ地方の親子のそれとを重ねて、鼻の奥がグズッとなった。
まさか、「ピノキオ」で泣くとは思わなかった。
ピノッキオとジェッペットさんは、さいごにはようやく落ち着くところに落ち着くのは、よく知られている通り。そこに至るまでのあれこれが、ディズニーふざけんなというくらいに、ものすごい。これは本書を読まないと分からない。要所要所で出てくる仙女とかなんなの、っていうくらい神々しい。萌えの元祖じゃないでしょうか。
『ピノッキオの冒険』は、うちの息子にも読ませたい。ただ彼は改心する前のピノッキオ級だから、本を見せただけでどっか川にでも釣りに行っちゃうかもしれない。君のそういうのはほんとに何とかならないんですかねとイラッとしつつも、ピノッキオみたいに悪いキツネとネコには騙されないでほしいと思うのは親心である。
『ピノッキオの冒険』は『文豪たちの釣旅』とあわせて読むと、感慨がさらに深まるのは、言うまでもないことです。
きちんと努力していけばきっと事態は好転する。
少しはましな明日がやってくる『文豪たちの釣旅』本文より

開高健 幸田露伴 井伏鱒二 坂口安吾 戸川幸夫 岡倉天心 福田蘭童 山本周五郎 佐々木栄松 中村星湖 立原正秋 尾崎一雄 森下雨村 池波正太郎