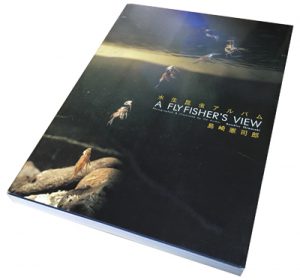いつも釣ってるこの川のオイカワは、出自をたどれば、おそらく西のほうからやって来たのが混ざっているはずだ。カワムツに至ってはつい最近転校してきたばかり。両方ともいわゆる国内移入種だ。
だからなんなんだ。
お友だちはマッカチンだのブラックバスだのニジマスだのミドリガメだの、生まれた時から生態系被害防止外来種まみれのわたしの人生だ。
オイカワの色付きのオスは見た目のインパクトが強いので、地方によって、釣り人によって、さまざまなニックネームをつけられる。『フライの雑誌』106号(品切れ)の特集アンケートでも、個性的な呼称がいろいろ挙げられていて面白かった。
先月取材に行った宇都宮では、色付いたオイカワのオスを「おしゃらくタナゴ」と呼ぶと聞いた。「おしゃれなタナゴ」という意味だという。宇都宮あたりにオイカワがやって来たのはせいぜいここ数十年のことだ。小洒落た新参者を、見知ったタナゴにひっかけたのだと思われる。
東北地方の一部でオイカワを「ジンケン」と呼ぶが、「ジンケン」は「人絹」、つまり「人造絹糸」で、ナイロンのことだ。ナイロンが身近になった時代に、オイカワも身近な魚になったということで興味深い。同様にオイカワを「シンチュウグン」と呼ぶ地方もあって、こちらは「進駐軍」から来ているという。
身近な魚であればあるほど、人間との付き合い方は多彩になる。それを文化と言う。
琵琶湖産コアユの全国河川への移殖放流事業が始まったのは1924年で、琵琶湖産オイカワも随伴してコアユとともに全国へ拡散した。そこから93年たったいま、琵琶湖産コアユの移殖放流事業は日本の内水面漁業の根幹を支えている。
いまの日本の川と湖から移入種を誰何して排除すると(そんなことは不可能だが)、残るのは生き物の気配のない月の砂漠のような水辺だ。まして公園の池やため池、農業用の水路に、現代のわたしたちはどんな自然を求めるのだろう。
なにごともバランスが肝心だ。
水辺をぶっこわしてしまえば、在来種だろうが外来種だろうが、人間だって生きていけない。わたしたちは日本の水辺をすでにさんざんぶっこわしてきた。これ以上ぶっこわさないことをみんなで考えよう。
昨日も川へ行った。




![『フライの雑誌』第106号|〈2015年9月12日発行〉| 大特集:身近で深いオイカワ/カワムツのフライフィッシング─フライロッドを持って、その辺の川へ。|オイカワとカワムツは日本のほとんどどこにでもいる魚だ。最近になって、オイカワとカワムツがとても美しく、その釣りは楽しく奥深いことを、熱く語るフライフィッシャーが増えている。今号ではオイカワとカワムツのフライフィッシングを、大まじめに真っ正面から取り上げる。この特集を読んだあなたは、フライロッドを持ってその辺の川へ、今すぐ釣りに行きたくなるでしょう。 新連載 本流の[パワー・ドライ] Power Dry Flyfishing ビッグドライ、ビッグフィッシュ|ニジマスものがたり](https://furainozasshi.com/wp-content/uploads/2015/09/106-cover-m-1.png)
大特集:身近で深いオイカワ/カワムツのフライフィッシング|オイカワとカワムツのフライフィッシングを、大まじめに真っ正面から取り上げました。この特集を読んだあなたは、フライロッドを持ってその辺の川へ、今すぐ釣りに行きたくなるでしょう。
新連載 本流の[パワー・ドライ] Power Dry Flyfishing ビッグドライ、ビッグフィッシュ|ニジマスものがたり


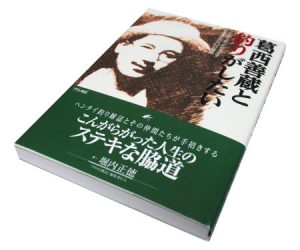
(『フライの雑誌』編集人)
ISBN 978-4-939003-55-4
B6判 184ページ / 本体1,500円
「友の会」会員は税込540円