○島崎憲司郎さんはいま、フライタイヤーとしての集大成、〈SHIMAZAKI FLIES シマザキフライズ〉の制作に取りかかっています。その現在進行形の姿をフライの雑誌-第113号で次のように紹介しました。
〈シマザキ・ワールド15〉(第108号)既報の通り島崎憲司郎さんはフライタイヤーとしての仕事の集大成と位置づけた〈Shimazaki Flies〉プロジェクトに集中して取り組んでいる。世間への露出を極力避けてスタジオへこもり、自らのフライタイイングへ愚直なまでに打ち込む姿勢は日を追うごとに鬼気迫るものになっている。
その島崎さんが9月下旬、突然都内へやってきた。上州屋八王子店とHIRANOTSURIGUを巡り、呆れるほど大量のフライマテリアルを買い込んで、風のように桐生へ戻っていった。明らかに〈Shimazaki Flies〉の仕込みに違いない。高品質の鳥類マテリアルにご執心のようだったが…。
誰も見たことがないシマザキフライズが姿を現す日まで、待つのみである。
(「シマザキフライズ・プロジェクトの現在 〈Shimazaki Flies〉はどうなっているのか」)
〈SHIMAZAKI FLIES シマザキフライズ〉の進行具合は、本誌読者はもちろんのこと、海外のフライフィッシャーまで気になっているらしく、編集部へはあちこちから(ほんとのところ、どうなってるの!?)という声が聞こえてきます。
○当編集部は、ふだんはぼんやりしていますが、いったん火がつくとしつこいです。というわけで、じつは昨日も桐生のシマザキデザイン・インセクトラウトスタジオと電話で長話しをしていました。
○最新の触りだけを伺ったところ、どうしようもなくすごいことになっていました。『水生昆虫アルバム』の執筆時もかくやというか、ひょっとしたらそれ以上と思わせるシマザキさんの熱量がガンガン伝わってきます。あれこれ話題が飛びまくった最後にシマザキさんがひとこと、「大丈夫。ちゃんとやってるから。」と言いました。
○骨の髄から釣り師のシマザキさんが、去年の夏に思いきってウェーダーを捨て、スタジオから仕事の邪魔になる余計な人払いをしてまで、「ちゃんとやってる」というのだから、推して知るべしです。
○さて、『水生昆虫アルバム』がすごすぎて渡良瀬川と水生昆虫の印象がつよい島崎憲司郎さんですが、じつはフライフィッシングの歴史上のきわめて早い時期から、日本全国はもとより海外のあちらこちらへフライロッドを抱えて釣りに出かけています。
○『フライの雑誌』創刊号(1987年)に掲載された、島崎憲司郎さんの「レッドアイリーチ」を本欄で公開します。今から31年前、誰もが気軽に海外へ行けなかった時代、当世一流のスティールヘッドの川、ノースアンプカ川でのスティールヘッディングの情景を描いた貴重な味わいぶかい作品です。
○若い頃にこんな風な大物釣りをさんざんやってきた島崎憲司郎さんだからこそ、水生昆虫のフライだけでなく、いかにも大物が食いつきそうな独特の大型フライのイメージもこんこんと湧いてくるのでしょう。第104号と、第108号に載っていた大型のシマザキフライがかもし出すド迫力(と、可愛らしさ)は別格でした。
○誰も見たことがないシマザキフライズが姿を現す日まで、待つのみです。
(できればなる早でお願いしますね、シマザキさん!)
ストリーム・パーフェクトに乾杯
(編集部)
・・・
レッドアイリーチ
Lead Eye Leech
島崎憲司郎
Kenshiro Shimazaki

1
「この一匹だけキープしよう、フレディにスモークしてもらうんだ。日本へのみやげだよ」
…デニスはそういいながらスチールヘッドを浅瀬によせ、バンダナを濡らして尾ヒレの付け根を素早くつかんだ。水際の草の上に引きずり上げる。白銀色に輝く立派な雄だった。デニスはバタバタ暴れる鱒の頭を石で二回叩いた。スチールヘッドはずっしりと横たわって、もう動かなかった。
シモダさんはこっちを向いて、やるせない顔をしてから「デシューツ川よりひとまわり大きいそうだね、ここの魚は。…しかし、呆気ないもんだねえ」と言った。
雨だった。朝からずっと降り続いている。身体が冷え切ってスパイクソールのウエーディングシューズが重い。九月も終わりに近づき、ノースアンプカ川の両岸に紅葉が始まりかけていた。
今釣ったこの大きな瀬のずっと上流にフェイマスプールという岩板底の巨大な渕がある。そこは淵というより、静かな沼を思わせた。その渕尻には滑らかに水に削られた岩瀬がせり出していて、川はそこから右に曲がりながら次第に流速を増し、ゴーロ帯に変わり、ガレ場の下を黒々と流れて枝沢を交え、やがて開けて川幅いっぱいに広がる長い平瀬へと続いていた。左岸から流れ込んでくる薮沢の奥にはクーガーが棲んでいるということだった。デニスによればフェイマスプールの流れ出しからこの辺までの変化に富んだ一帯がこの川で最高の釣り場だそうだ。ぼくたち三人は今朝、そのフェイマスプールから入ってここまで延々と釣り下ってきたのだった。
ダグラスファーの森をしばらく行くと、ひっそりした広場に出た。片隅にくたびれた白のワーゲンがとまっている。燻製作りの名人、ファット・フレディはそこでパイプを燻らせていた。あだ名通りのタイコ腹。帽子のぐるりに大ぶりのウェットフライをビッシリ刺している。
デニスは、さっき釣ったスチールヘッドを見せて「こいつを頼む」と言い、ぼくらの方を向いて「日本の友達だ」と言った。フレディはうなずくとフライロッドで川の方角を指しながらパイプ越しに何か言い、両手を90㎝ほど魚の形にひろげて首をすくめ、ワーゲンのドアを開け、デニスのスチールヘッドをリアシートに放り込んだ。冷蔵庫にビールでも入れるような手つきだった。そうしてロッドを手に川の方に去った。
「いい奴なんだが…」とデニスが言った。聞くところによると、彼氏ときたら釣ったスチールヘッドを全部スモークしてしまうらしい。
ぼくたちも再び次の釣り場へ向かった。

2
デニスのキャスティングは筋金入りだった。投げにくいフライだろうが投げにくい場所だろうが、とにかくスチールヘッドのいるところならどこにでもフライを送り届けてやるんだという気迫がこもっている。それでいながら、目と目が合うとニコッと微笑むのだ。それは何十年か前の彼の少年時代を思わせる一瞬だった。それにしても、あれだけ重いフライをよくあんなふうに投げられるなと思う。このフライというのがちょっと普通でないので、後で色々と説明してみるけれど、何しろパチンコの玉くらいの目方があるのだ。
見ていると、デニスは(まず自分の下流側に適当な長さのラインを伸ばし、水流で張っておいて)方向転換を加えたロールキャストの要領で7〜8ヤードのラインを正面または投げたい方向の水面に伸ばす。と同時にこれを滑らかに後方に引き抜く。スローモーションのようにバックキャストが伸びる。シューティングヘッドがトップガイドから出てバックラインが一直線に張る。そのドンピシャのタイミングで一気にパワーをかける。ボロンロッドがギュンとしなる。ループは鋭く尖っていてスピードがあるのでドライフライを投げているかのようだ。レッドアイリーチは大アンプカ川の遥か対岸ぎわまでカッ飛び、13フィートのリーダーがきれいにターンして流れに吸い込まれるのだった。何度やってもトラブルなし。
「凄いや、レフティ・クレーよりうまい」
「そうかね、彼にそう言っとくよ」
シューティングヘッドに何か工夫を凝らしているのかなと思って聞いてみたら、8番のフローティングで長さは30フィート、ランニングラインは30ポンドテストのフラットモノフィラという種も仕掛けもないものだった。ロッドはオービスの8フィート9インチの#7。リールはサイエンティフィック・アングラーズのシステム2の78というゴツイやつで、ぼくたちもお揃いでこれを使わされた。ドラッグ機構がしっかりしていて頼りになるリールだ。これはスチールヘッドをかけてやりとりしてみると納得する。ぼくはこの日の午後、雨上がりの明るい日射しの川の中で初めてそれを実感した。スチールヘッドが一気にラインを引き出した時のクリック音も軽快で気持ち良かった。

3
一日の釣りを終え、どっと疲れてスチームボートインのテラスで三人で飲んでいると隣室のメル・シンプソンが川から帰ってきた。
「今日はダメだ」「一杯やる?」「もちろん」「これ食うかい…ナリタで買ってきたんだ。硬いぜ。貝柱の干したやつだよ」
フライの話になった。メルはちょっと見せたい物があるので部屋からとってくると言って、しばらくすると大事そうになにか持ってきた。バイスだった。その形は一種独特でバイスというよりガスバーナーを思わせた。彼がそれをスタンドの明かりの下にうやうやしく置くと渋い胴色に光った。「俺のバイスを見てくれ、どうだ全然違うだろう」とメルは言い、前代未聞の特製バイスの彼いわく『画期的な』特徴をこと細かに説明しだした。「なるほどな」 「七年掛かりなんだぜ」 「で、これの名前は?」 「ストリーム・パーフェクト!」 メルは胸を張り、次に無邪気に笑った。
その晩のフィッシャーマンズ・ディナーでメルは奥さんを連れて釣りに来ていることをぼくは知った。どことなくやつれた影の薄い女性だった。いつも床か天井か壁かをうつろに見ている。メルは夫人とはあまり口をきかず、もっぱら釣りのことばかり喋り、デザートになってもワインを手放さなかった。
ディナーの後、一人帰り二人帰りして、メルとぼくだけが残った。
「デニスたちは?」「とっくに帰ったさ。なんでTMCはダウンアイのサーモンフックを出さないんだ。ダウンアイの方がいいんだぞ」
「そうかな」「アップアイなんかダメだ」
「でも今日ぼくはTMC7999でスチールヘッドを釣ったけど…、それに、あのフックのアップアイは今までのとはちょっと違うんだ」「ウンニャ…ダウンアイだ。おまえのファクスナンバーを教えろ、何番だ? もう一杯やろうぜ…スチールヘッドに乾杯」
そうとう行ける口らしかった。「スローアクションのフライロッドなんか俺は大嫌いさ」と言い、ティペット・マテリアルの話になると「俺はマキシマしか使わないんだ」と言った。ぼくは、フトあのガスバーナーみたいなバイスのことを思い出した。そうしてぼくはメルのバイスに対してまだ何の批評もしていなかったことを今になって気付いた。さっきは何しろどっと疲れていたし、それにぼくたちは空腹だった。そこへ、スコッチである。メルがバイスを分解して、このスプリングは、このピンは、このネジは、と七年の洗練を開陳しても、ぼくら三人はグラス片手に貝柱を噛み噛み「なるほどねェ」と「ホウ」を繰り返していただけだったのである。そういえば、…あの時、ドアの外に誰かがいたような気もする。どうもあれは女の人らしかった。すると、メルの奥さん…(!) 悪いことをしたな。ぼくはポケットから紙と鉛筆を取り出した。メルのバイスの絵を描く。メルは途端に真顔になってグラスをテーブルの上に置いた。ぼくはこれまで使ってきたいくつかのバイスと比較して、メルのバイスの優れた点を指摘した。ここと、ここと、それにここのところ。実によく工夫されている。一朝一夕では出来ないことだ。あなたのバイスは実に素晴らしい。
「ストリーム・パーフェクトに乾杯」
部屋に帰る時、彼の車に案内された。トヨタの4WDのピックアップだった。メルはヨレヨレのベストのポケットからフライボックスを取り出し、一本ずつ慎重に選んで5本のフライをぼくに差し出した。そのうちの一本はデシューツ・スペシャルで、あとのは自分のオリジナルらしかった。なるほど全部ダウンアイのフックを使っている。バーブは全てつぶしてあった。いかにも彼らしい個性の強いタイイングだったが、月明かりの中でも一見して年季の入ったフライタイヤーだということがすぐ分かる。メルのフライは全体に薄目の巻き方でパラリとまばらなヘアウイングが急角度に立っている点に特徴があった。フライなんて物は、こういう風に一人一人違うところが面白いのだと思う。
4
6と書かれた木のドアをそっと開けるとシモダ氏はすでに大の字になって寝ていた。
さてと。タイイングでも始めるか。明日のために今日の当たりバリを巻くのだ。霜田さんのも巻いておこう。彼は知る人ぞ知るフライフィッシング界の秀才で、ぼくより二○倍ぐらいアタマがいいけれど、こういうことにかぎってはぼくの方が一枚上手だ。
ブラック&パープル・レッドアイリーチ#4…なんて言うと何だかもっともらしく聞こえてしまうが、実は昨晩ありあわせの材料で泥縄式にでっち上げた代物である。しかし奇妙に釣れそうな気配がしてならなかった。実際あのスチールヘッドはまさにこれにきたのだった。紫色のシェニールがよかったのかな。
スチールヘッドは紫色を好むという説がある。出発の前日にそれを霜田さんから電話で雑談中に聞いた。紫のシェニールがいいんだとかいっていた。気にも止めなかったがさて床につくとどうにもそれが頭の片隅から離れない。まあ重いものじゃなし、持っていくか。起きだして問題のものをガサゴソ探す。ところか何としても見つからない。おかしいな。さてこうなると余計に欲しくなるものだ。もう全然寝られない。紫色のシェニール。紫色のシェニール。仕方がないので白いやつを染めることにする。結局、夜が明けてしまった。
そうして着のみ着のまま、眠気まなこをこすりながらこのオレゴンまでやって来たのだった。
本当のところ、あのフライがスチールヘッドを引き出したのは紫色の魅力なのだろうか。…どうもそうではない気がする。色のおかげも少しはあったかもしれないけど、それよりもむしろ「生き物らしい動き」が物を言ったのだと思う。さっきレッドアイリーチと言ったが、このレッドアイとはつまり「鉛の目玉」(Lead Eye)なのである。だからこれを取りつけたフライは重心が極端にヘッド寄りになって、水の中でただならぬ動きをするのだ。
レッドアイリーチとは生まれてからまだ一年ちょっとのパターンで、言ってみればオスカーリーチの雄とウーリーバガーの雌とを交配させたような新種の大物キラーである。…これですぐ想像がつくとおり、このフライは、あんまりお上品でないタイプに属する。それでいながらどこか愛嬌があって可愛らしくさえあるのは、これまたレッドアイのせいであるらしい。まるでレイバンのサングラスをかけたような顔つきなのだ。タモリみたいなのである。もともとはバス用のパターンなのだが、これをスチールヘッドに使い始めたのはデニスが最初だったそうだ。今ではこの川筋のスチールヘッダー達の切り札になってしまった感がある。実際、ホントに良く釣れるのだ。そういえば、さっきのファット・フレディに「あなたの帽子は色とりどりのスチールヘッドフライで満艦飾だけど…どのフライが一番釣れるんですかね」と訊いたら迷わず黒のレッドアイリーチを抜き取ってニッコリしてみせた。決まってるじゃないか、そんなこと…そういう感じでゆったりとパイプをふかし、ウサギの毛のふわふわしたテイルのあたりを指先で撫でたりした。
レッドアイ自体の形は、真ん中がくびれた糸巻きボビンに似ている。大きさは米粒ぐらいのものからピーナツほどもある特大サイズまで四通りあって、地元勢はみんな特大のやつを使っていた。この川は、立ち込んでみると見た目より遥かに流れが強いので、そのくらいの目方がないと流圧に負けてしまうのだろう。ウエーディングするのが本当に怖いところがやたらとある。水自体が普通より重たいのではないかと感じるほどだ。
しかしそれにしても、こんな破廉恥な物を思いついたのはどこの誰だか気になるところだ。デニスに聞いたら、ワプシというフライフィッシング関連の会社をやっているトム・シュマッカーという人物とのことだった。すぐ考えつきそうなアイデアだと言ってしまえばそれまでだけれど、それを即座に形にして売り出してしまうところがいかにもアメリカらしくて愉快だなと思う。実は、ぼくも随分前に同様のものを自作してドラゴンフライのニンフやマイクロミノーに使っていたことがある。ぼくのはガン玉を釣り糸にジュズつなぎに止めて2個ずつ切り離しただけの素朴なやつだったが、原理的には全く同じである。そんな経緯があるのでぼくはこのレッドアイをオレゴンに来て初めて見たとき、内心ニヤリとして「こいつは面白いぞ。帰るまでに少し分けてもらおう」とは思っていた。のだが、実際にデニスがそのフライでスチールヘッドをガンガン釣りまくるところを見てしまうともうそんな呑気なことではすまなくなった。もちろん彼は自分のレッドアイリーチを何本かくれたのだったが、ドジなぼくは使っているうちに結局全部なくしてしまったのである。また「くれ」というのもちょっとねェ。それにぼくは人様のフライで釣ると、どうもしっくりこないタチなのだ。全然釣れなければ我が身の至らなさを自分で証明しているようなものだし、釣れれば釣れるでなぜかケタクソわるい。自分で巻いたやつで釣りたいなと思った。それには問題の目玉がついていないと始まらない。
「ボク、コレ欲しい。スグ欲しい。タークサン欲しい」
これは出来ない相談ではなかった。なにせ彼は全米を股にかける大手フライフィッシング用品会社のボスなのである。

5
アンプカ・フェザー・マーチャンツ社のオフィスはフカフカの絨毯が敷き詰められていた。デニス・J・ブラック社長はスパイク付きのウエーダーのままでクリーム色の絨毯を踏んで入った。ぼくらも言われるままにそのあとに続く。何人もの若い女性がコンピュータやテレックスを操り、壁には巨大な鮭の剥製や海の大物釣りの写真やデイブ・フィットロックから贈られたバスフライの額やらが掛かっていた。二人の男がボートの上に立ち、一方の男はフライロッドにしがみついてのけぞり返り、その向こうの水面では恐らくサメかワニかのどちらかが暴れ狂っていて、その怪物を狙ってもう片方の男が構えた大型拳銃がまさに火を吹いている、というようなド肝を抜かれる写真もあった。
男のスタッフは明らかに全員がフライフィッシャーだった。奇特なことに、みんなぼくのフライタイイングに前々から興味しんしんとのことで、実際に巻くところをぜひ見たいと言う。適当に五~六本巻いて見せたところ、どういう訳か皆さん目を丸くしている。
ぼくはそんなことには上の空で、お目当てのレッドアイをポケットに入り切らないほどいっぱい貰ってニコニコしながらこのスチームボートインに帰ってきた。
そうして昨夜そのレッドアイでくだんのフライを巻き上げ、そのうちの一本に今日の午後90㎝の雌が炸裂したのだった。そんなわけで、こうして明日用にそれと同じやつを巻いているというわけなのだ。
窓の外からは相変わらずノースアンプカ川の瀬音が聞こえてくる。風が少し出てきたようだ。シモダさんはぐっすり寝ている。そういえば、あのスチールヘッドは今頃どこでどうしているだろう。鉤を抜いたあとがまだ痛いだろうか。リリースするとき、右の胸ヒレをちょっと触ってしまったけれど、あれはまずかったな…。あの時は「ヒレに触るな!」とデニスが大声で叫んだものだ。それから、しんみりとこう言った。
「鱒を川に帰す時は、絶対にヒレを触っちゃいけないんだ」
5本目を巻き上げたら猛烈に眠くなった。時差のせいだろうか。水を飲んだ。寒い。もう1本巻いた。そうしてそのままベットに潜り込んだ。
朝になった。いい天気だった。オレゴンの秋晴れだ。テラスで釣りの支度をしていると背後に人の気配がした。ふりむくと少壮の男が黒い犬を従えて静かに立っていた。右手にスチールヘッドをぶら下げている。左手で犬を制し、お座りさせた。目映い朝日の中に釣り人と猟犬とがシルエットになり、光線の加減でスチールヘッドだけが銀白色に鋭く光って対比している……。
さて、行くか。今日で終わりだ。デニスはきのうより少しゆっくりと車を走らせた。ジョージ・ウインストンのアコースティックピアノとサンルーフから吹き込む九月の風が爽やかに調和してすがすがしかった。ぼくたちは木の葉の色がきのうより一層あざやかになったことを言い合いながらフェイマスプールに向かった。
※初出『フライの雑誌』創刊号(1987年5月発行)

Photo: Kenshiro Shimazaki



○天国の羽舟さんに|島崎憲司郎
○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在
○連載陣も絶好調
・・・
『フライの雑誌』第113号
本体1,700円+税〈2017年11月30日発行〉
ISBN 978-4-939003-72-1 AMAZON


身近なビッグゲーム 中村善一×島崎憲司郎 異分野対談
画家の視線とシマザキワールド 後篇
○ニジマスものがたり 最終回 ─研究者として、釣り人として 加藤憲司
○連載陣も絶好調
・・・
『フライの雑誌』第112号
本体1,700円+税〈2017年7月31日発行〉
ISBN 978-4-939003-71-4 AMAZON

シマザキ・ワールド13 島崎憲司郎|
マシュマロ特集
SHIMAZAKI WORLD13。オリジネーターの島崎憲司郎さんによるマシュマロ誕生秘話、マシュマロ・ピューパのタイイングのコツと写真解説、オポッサムのコラムも。最近のバックナンバーではクロスオーストリッチ特集の第90号と同じくらい、いちばん売れている号。
text&photo by Kenshiro Shimazaki

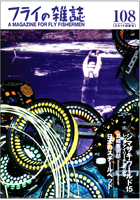
レッドアイリーチから30年
島崎憲司郎
Shimazaki World 15
Kenshiro Shimazaki
島崎憲司郎、2年ぶりのシマザキ・ワールド最新版。期待が渦巻く[Shimazaki Flies]プロジェクトの本人による経過報告と2016シマザキフライ
