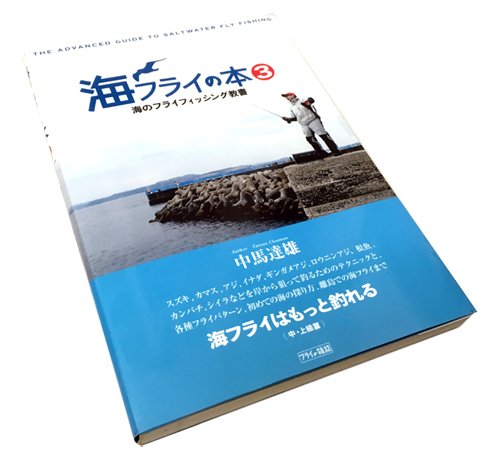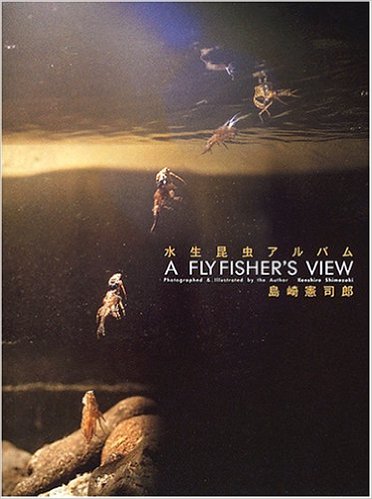急に釣りがしたくなって、山梨県の小菅川へ行った。
いま「急に釣りがしたくなって」と書いた。これは不正確な表現だ。なぜなら自分は「常に釣りがしたい」からだ。
釣り師の言うことを真に受けてはいけない。

小菅川特設釣り場は今季のオープンから間もないのに、すでにむちゃくちゃスレていた。スレ具合が度を越すと、水温やハッチとは関係なく、沈めるフライよりも水面の釣りのほうが魚の反応がよい場合がままある。今回もそんな感じで、水面のフライだけで釣り通して満足できる結果を得た。最新号で水面の釣りの特集を組んでいてよかった。

たとえばこの写真のようなフォルムの崩れた我ながらよく分からないフライでも、水面というフィルターを通すと魚には食べ物に見えるらしい。あと重要なのは流れと風。止水風のプールで粘るのがいちばん難しい。小菅ではへたするとふつうにボウズを食らう。歩け歩け。

20番のショートシャンクのフックへごく小さめに薄く巻いたエルクヘアカディスを巻き返しに浮かせたら、水面からじんわりと魚の鼻先が出てついばむようにしてそれを食った。出会いはスローモーション。軽いめまい誘うほどに。それを(んむもわあっ!)と心のなかで変な声で叫びながらゆっくりと、ゆっくりとアワセたのはわたしの熟練の技だ。会心の一匹。けっこう引いた。
かなり離れた下流で釣っていたりょうたさんが後で寄ってきて「相当引いてましたね、取り込むの苦労していましたね」と言ってきた。見ていてほしいな、と思ったらやっぱり見ていてくれていた。遠目でも確実に分かるように大げさにランディングしたのであった。わざと転倒してやろうかと思ったくらいだ。
釣り師なら誰しも自覚があるだろうけど、ある程度以上の釣り師どうしは離れて釣っていても、相手の釣りの状況をなんとなく把握しているものだ。あ、いま釣ったな、とか、あ、バラシたな、とかを背中や横目で無意識に観察している。見えなくたって雰囲気でわかっちゃう。
その超人的能力を社会的な実務に活かしたならば、釣り師にも違う人生があったはずである。だがいかんせん、釣り師は水辺でしか超人になれない。いやこう言おう。水辺の釣り師は超人である。

お互い約束なんかしていないのに、秩父の人間重機内田さんと平日の小菅川でばったり会うというありえない奇跡が起きた。世界じゅうの誰よりきっと僕らはつよく惹かれあっている。まじか。
内田さんはバリバリ釣っていた。あのしぶい状況の小菅で、水面だけで二けた釣ったという。すげえなあ。おれは遊び半分でやってたったの9匹だったよ。

小菅に来たら廣瀬屋旅館さんのランチを食べたい。小菅村の人は釣りびとにやさしい。気持ちいい釣り場の条件は、川がよくて魚がよくて人間がいいことだ。誰だか知らないが地元然とした一群の人々が横暴なふるまいをする川は遠慮したい。(けっこう根に持ってるみたい。釣りの恨みはおそろしい)。

東京都の水源林になっている山々の紅葉が美しい。釣り師もときには山を見る。




○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在AMAZON