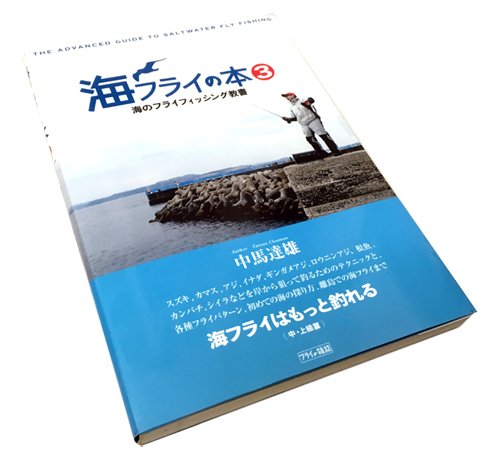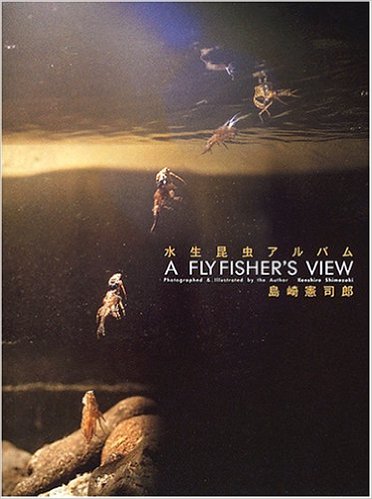フライの雑誌-第112号(2017 品切)より、〈釣りはハプニングが面白い〉(堀内正徳:あとは現場で 改題)を公開します。
掲載当時、肥大化する一方の高度情報化社会の陥穽を貫く、現代のロンギヌスの槍だとして、大いに話題になった作品です。
・
釣りはハプニングが面白い
堀内正徳(本誌編集部)
・
担当編集者とふたりでどこか知らない街へ取材に行って、昼飯時になったとする。そこでいきなり携帯で「食べログ」とかチェックする編集者を、僕はぜったい信用しない。他人の意見に従うのではなくて、とにかく自分で選んで、食べてみる。そこで最悪の飯が出てくるかもしれないし、いままで食べたことがないようなおいしいものに出会えるかもしれない。(『圏外編集者』都筑響一)
わたしは平成始めのころ、中途半端なダンドリくんだった。デートする前は一応雑誌とか開いて理想のコースを描いて段取りを組む。妄想する。ところが人生には想定外のことが起きるものだという、諦念というより期待は人一倍あるほうで、あとは現場で、と途中で投げっ放してしまう。そんなデートはうまくいくときもあった。うなくいかないときはもっとあった。
たしかにここ数年、誰かと待ち合わせをすると、「食べログ」のアドレスが送られてくることがあるし、自分でも「ここどうでしょう」のコメント付きでお店を提案することもある。大切な相手を連れて知らない店へ適当に入り、最悪のご飯が出てきたら、ふつうに困る。便利なものは便利なのである。
○
大岡玲さんと初めてお会いすることになったとき、待ち合わせ場所に高尾の浅川国際鱒釣り場を、わたしが指定した。一緒に釣りをすれば、喫茶店で百回会うより相手を理解できるというのが、わたしの持論だ。
ただし季節は真冬だった。しかもわたしはそのころ足を骨折していた。頭おかしい。けれど釣りの雑誌的に、街で会ってもつまらないだろうと思った。釣り師としての大岡さんの佇まいを、自分の目で見たかった。
約束の時間少し前に、釣り場への凍りついた坂道を下っていくと、大岡さんはもう着いていて、雪の積み上がった極寒の池の畔で一人で先に釣っていた。小さなニジマスを釣り上げてフライロッドの先にぶらさげ、ばかみたいな笑顔で喜んでいる大岡さんを見て、試すようなことをしてすみませんでした、と思った。
昼ご飯どきになり、話題のお店がありますからと、自分では入ったことのないお店へわたしが先導した。が、甲州街道沿いにあるお店の駐車場には定休日の札。やっぱり中途半端。ワインと美食の本を出しているほどのそのスジの方をどこへ連れて行けばいいのか。
大岡さんの車を引き連れたまま、甲州街道を憮然として東へ走った。ここから先俺どうすればいいんだろうね。ふと蕎麦屋さんの看板が目に入った。このとき初めて気づいたお店だ。釣り師の野生のカンが働いた。フォースを信じろ。
「少しつかれたね、休憩したいな、いいでしょ」とでも言うようにさりげなくハンドルを切ってインした。するとこれが大当たり。大岡さんとの会話も弾んだ。
大岡さんの『文豪たちの釣旅』をフライの雑誌社から出すことができたのは、あの日のお昼ご飯の小さなラッキーを、二人で共有できたからだと思っている。
○
現代社会ではインターネット上のぼう大な情報を活用しない方が、奇人・変人・原始人と呼ばれる。遠征の釣り場選びも、最新の状況をふくめて他人様の評判をネットで検索してから出かけるのが普通で、わたしだってそうする。
でも便利さのかわりに喪うものもある。とくに趣味の場合では。
今年の6月初旬。ふと、事前情報まったくなしの釣りがしたくなった。中央道を松本を越えてさらに西へ走り、大きな川沿いに下り、地図と山の形を照らし合わせて、一本の支流を選んだ。
入渓前に上下流を往復して、退渓点をふくめた川の様子をうかがうという、渓流釣りの基本動作を久しぶりにやった。
『Angling』創刊編集長の山田安紀子さんは、「釣りはハプニングが面白いのよ。」とおっしゃっていた(本誌第87号) 。しょせん人間のやること、自然相手ならなおのこと、ハプニングだらけに決まっている。素敵なハプニングに出会いたくて釣りなんかしてる。たまにうまくいったときのうれしさは百万倍である。

夏アマゴ。魚のサイズは気にしないが、何度測っても29.5センチ!

真っ昼間、写真の流れの左上、瀬の真ん中にマシュマロパラアントを投げた。流れくだって浅いヒラキに差しかかかったところで、水面を押さえ込むようにして魚が食った。大物はいつも一発目にくる。

初めての川で使うパイロットフライには、使いやすさと汎用性と信頼感が大切。

この日はマシュマロ系で通した。

第112号より(品切れ)

フライの雑誌-第116号 小さいフライとその釣り 隣人の〈小さいフライ〉ボックス|主要〈小さいフック〉原寸大・カタログ 全88種類|本音で語る〈小さいフライフック〉座談会|各種〈小さいフライフック〉の大検証|〈小さいフライ〉の釣り場と釣り方の実際|〈小さいフライ〉エッセイ 全60ページ超!
70年ぶりの漁業法改変に突っ込む|もっと釣れる海フライ|新刊〈ムーン・ベアも月を見ている〉プレビュー掲載
第116号からの【直送便】はこちらからお申し込みください 2019年2月14日発行







○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在AMAZON