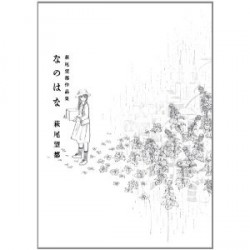ファンだと思っているくせにもう何年も雑誌掲載で追いかけていなくて申し訳ないと思いつつ、萩尾望都さんの単行本『なのはな』をやっと読んだ。
表題作「なのはな」は震災からわずか3ヶ月後の(!)去年の6月に発表された。
本のオビに作者萩尾望都さんのこんな言葉が書いてある。
「あの日」から、私は胸のザワザワが止まらなくなった。
主人公である福島の小学生ナホちゃんはあまりにかわいらしく、彼女の3・11以降の日常はあまりに切ない。しかもその切なさは漫画のなかの造形ではなくて、フクシマ(作品中では繰り返しカナのフクシマが使われている)の後を生きているすべての子どもとおとなへ、ひとしなみに否応なくふりかかっている現実だ。そこに思いをやると胸の〝ザワザワ〟が止まらない。
そもそもバタ臭さでは余人の追随を許さない白い瞳を持った萩尾キャラたちの絵柄と、彼ら彼女らが操るばりばりの福島弁は、まったくそぐわないことこのうえない。だからなおのことその非現実感とリアルが背中合わせになって、〝ザワザワ〟がいつまでも消えない。大島弓子さんは〝サワサワ〟、萩尾望都さんは〝ザワザワ〟。濁点のあるなしでこうもちがう。
併録「プルート夫人」「雨の夜 ─ウラノス伯爵─」「サロメ20××」の〈放射性物質三部作〉のほうは、タイトル通りで放射性物質を擬人化した連作。もちろん萩尾望都さんなのだから絵はすばらしく上手い。しかしまったく寓話になっていない。萩尾望都の大天才をもってしても3・11の原発事故は、そうやすやすとは作品として昇華できなかったのだろう。プロレタリア文学の代表的な失敗例のようで見るに耐えない。
この連作に価値があるとすれば、去年の3月に福島原発がまき散らした放射性物質が、将来地球上からなくなった時に、大昔の天才があの時代にこんな漫画を描いていたと、古文書的に再発見されることか。それはいつかというと、おおむね10万年後だ。そこまで人類が生き残っていればだけれど。
3・11は表現者を二分した。自分のこととして真正面から受け止める、もしくは受け止めようとして呻吟するひとと、なんだかんだと理屈をつけスルーするひと(福田和也さんのように)。だれもが〈語らなければいけない〉かといえばまったくそうではない。ただ同時代人として〈語るべきひと〉はいるとは思うし、本人はそれをわかる。
あとで安全地帯からコメントするならだれにでもできる。萩尾望都さんは逃げなかった。たとえ生ゆでのパスタであっても、そのまま描ききったところがやはり萩尾望都の天才なのだ。
世界が終わらないように、世界が次の世代に続くように、願っています。
(あとがきから)
ところで本作の初出誌『flower』の版元は小学館。『SAPIO』と『週刊ポスト』の小学館であるから、さすが大手は奥が深いなあと思った。