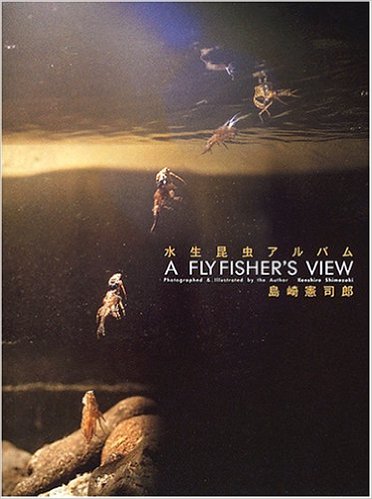今週末、わたしは信州できれいなアマゴをたくさん釣って、わーい、とか喜んでいた。そのあいだ近所の小学生は、「ゲームをしないで読書するのはなぜ良いか。」をテーマに作文しなさい、という学校の宿題を持ち帰ってきて、大いに悩んでいたらしい。
この小学生が保育園児だったころ、担任の保育園の先生が保護者会で、「ゲーム脳」の害悪と恐ろしさを記したプリントを配布して中身をひとしきり引用し、親の意見を求めた。するとわたしの隣りに座っていた若いお父さんが、まっ赤な顔をして黙りこんだ。うっすらなみだも浮かんでいたように見えた。わたしは彼の職業がゲームデザイナーであることを知っていた。
だからというわけでもないが、挙手して「ゲーム脳という考え方にはトンデモ批判もありまして、」というようなことを、あまりよく知らなかったけれど、わーわーと発言した。とても素敵で有能だった保育園の先生は、「それは知りませんでした。わたしももっと勉強します。」と言ってその場はおさまった。
大岡玲さんによれば、大正時代末期から戦時中の「国語現代文」試験は、受験生の人物考査としての機能を内包していたという(「国語」入試の作り方)。わたしは子どものときに国語の点数だけはよかった。それは出題者の意図を忖度するのが得意だったと同じ意味だ。「どうせこういうことを書かせたいんでしょう。」とおとなが喜びそうな回答を書けば、高得点は約束されていた。自分ながらいやな子どもだと思うが、いやな子どもなほど高得点を与えるシステムを作って回しているおとなの方が、もっと悪徳であろう。け、べらんめえ。
話を戻すと、「ゲームをしないで読書するのはなぜ良いか。」というテーマで作文させるのは、思想教育に近いとわたしは思う。でなければ一律的な価値基準の押しつけだ。耳ぎこえのいい表層を深慮なく妄信するのはゲーム脳ならぬ、文科省推せん脳である。そういう「よい先生」を多くしようとして国はここまでやってきたところ、そのかいあって近年は「よい先生」がずいぶん多くなったようだ。
「ゲームはほどほどに時間を決めて友だちと楽しみます。読書を通じて知らない世界を知りたいと思います。」とでも書けば、文科省推せんの「よい先生」は合格点をくれる。ゲームでだって知らない世界を知ることはできるけどね。ダンジョンとかいろいろあるし、とへりくつこねるのは、「わるい先生」だ。
小学生は、自分ではあまりゲームをしない。読書を好んでいるわけでもない。だから「ゲームをしないで読書するのはなぜ良いか。」と言われても、ちんぷんかんぷんだ。また彼は、子どものころのわたしのようないやな子どもではなくて、むしろ透明度2メートルくらいの分かりやすいばかである。興味のないことを書けと強制されても、一文字も書けないまっすぐなこころを持っている。
頭を抱えている小学生がかわいそうになったわたしは、励ますつもりで声をかけた。「あのな、ゲームと読書は対立する概念ではないのだよ。だからこういう宿題をだす先生の方が、おれはおかしいと思う。」と、小さな肩に手をおいた。すると小学生は机に突っ伏したまま、「いいからあっち行って」。
こういうとき、わたしのアドバイスは1ミリも役に立たないと体験的に知っているようだ。彼は小学生ながらに筆を折りたい気分だったろう。葛西善蔵なら酒でもあおったところだ。
大岡さんは先の文章を、〝戦後の「国語」はきわめて民主的で素晴らしいものになったか、というと、はてさて、どうなのだろうか。〟と結んでいる。昨日のわたしも、まさに「はてさて、どうなのだろうか。」とつぶやきながら、あっちへすごすごと退散したのだった。
アマゴ釣りから帰ってきたばかりだけれど、ハヤ釣りでも行くか。





シマザキデザイン・インセクトラウトスタジオのアシスタント山田二郎さんによる〈シマザキ・ガガンボ〉最新版のタイイング。ストレッチボディとマシュマロファイバー、CDCで構成されている。シンプルでユニーク、使い勝手は最高。次号で紹介。
2019.12. 26.桐生にて

フライの雑誌社が初めて出展します。
第31回 つるや釣具店 ハンドクラフト展
2020年 2月21日(金)、22日(土)、23日(日)

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄
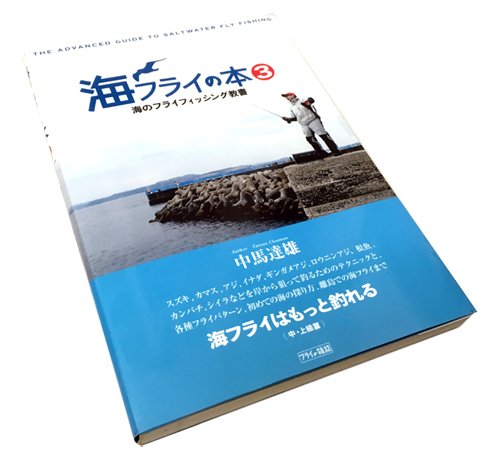

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。


フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川