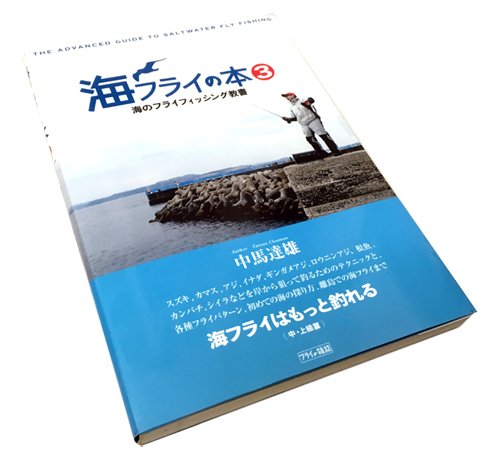20代の前半までは会社員だった。季節労働に近く出張する機会が多かった。夜は課長のお伴で、課員数人が連れ立ってご当地の歓楽街へでかけていく。ビロード張りの丸い椅子に座った薄着の女性がお酒を注いでくれる系統のお店が目当てだ。巷にまだバブルの残り香がただよっている頃である。
案内所とか食べログとかないし、お店探しは野性のカンに頼る。夜の帳のおりた歓楽街をうろうろして、それらしいお店に目をつける。重いドアをそうっと開け、中の様子をうかがって課長に報告するのは、若者の役目だ。斥候である。
店内を覗いて走って戻ってきたわたしが、「ここ大丈夫です!入りましょう!」と先導し、みんなで意気揚々とお店へ入る。課長の十八番は「長崎は今日も雨だった」。あとは「マイウェイ」「別れても好きな人」。
課長がお店の女性とうれしそうにデュエットしていたので、喜んでもらえたんだなと思っていると、お姉さん方に見送られてお店を出て、歩き出したとたんに、後ろからバシーッと頭をはたかれた。
「ばかやろ。あんなのスナックじゃなくて動物園じゃねえか!」
怒られることがたび重なって、わたしは斥候役から外された。わたしの好みは課長に合わなかったようだ。以来、ほかの若者がわたしの代わりに元気よくお店へ突っ込んでくれることになったのはありがたかったが、だんだん会社の中に自分が居づらくなっていった。
ある日、北関東のスナックで、きれいだなあと思えるお姉さんに会った。わたしはドキドキしながら、対面へ膝をずらして斜めに座ったお姉さんから、茶色いお酒をついでもらった。呑めないのに。
お姉さんはタバコに火もつけてくれた。ライターを両手で支えたお姉さんが、白くて長くて細い腕を伸ばすと、夢みたいないい匂いがふわりとたった。灰皿ですぐに消して、また火をつけてもらってむせた。ちなみにタバコはとっくにやめた。
きれいなお姉さんはわたしに言った。
「ねえ、お客さん。ハマショー歌えるでしょ。ねえ歌って、ハマショー。」
歌えないですー、と言ったら
「うそー。ぜったい歌える。似てるもの。ねえ歌って、ハマショー。」
と重ねて乞われた。おれ似てるのか。ハマショー歌えないといけないのか。帰ってからCD買おう。
そのお店できれいなお姉さんはお姉さん一人だけだった。あとは強力な親戚のおばちゃんみたいなのが、ずらりとそろっていた。課長は親戚のおばちゃん二人に左右から両腕をとられて、気持ちよさそうに「マイウェイ」を歌うのだった。
課長はなぜかそこのお店が気にいったようだった。わざわざ出張する用事をつくって通いこんだ。わたしが一緒に出張するときは毎回連れて行かれた。
きれいなお姉さんに会えたのは、残念ながら最初の一度きりだ。せっかく覚えたハマショーを、わたしが熱唱することはなかった。
単身赴任中の課長は都内のアパートで一人暮らしだった。一度泊めてもらったら、写真館で撮ったらしい家族写真がピンク色の額縁に入れられて、アパートの玄関に飾ってあった。
椅子に座っている、眼鏡をかけた地味目な奥さんの後ろに課長が立ち、セーラー服を着た娘と、生意気そうな中学生の息子の肩に手を回して、課長だけ満面の笑みで写っていた。
わたしが会社をくびになって数年たったころ、課長が離婚したと風の噂に聞いた。さらに何年かたって今度は課長が会社を辞め、同時に再婚したと聞いた。どこかのスナックのママと、足立区の外れで二人で暮らしているのだという。
課長ではなくなった課長の携帯電話に電話してみた。
1コールで出た。
「おう、久しぶりじゃねえか。元気でやってるか。」
と、変わらなかった。



○天国の羽舟さんに|島崎憲司郎
○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在
『フライの雑誌』第113号
本体1,700円+税〈2017年11月30日発行〉
AMAZON