『葛西善蔵と釣りがしたい』を評価してくれた荻原魚雷さんが、こういう風なことを書いてくれた。四釜裕子さんにはなんとわたしの絵をほめてもらえた。尊敬する方に自分の名前を出してもらうのはものすごく恥ずかしくてありがたくてうれしい。
わたしはここ数号の『フライの雑誌』の誌面を素敵な情況だと思っている。連載陣、単発記事、特集で誌面作りへ関わってくれる方々すべての皆さんがとても気持ちがいい。10代の頃から自分が作りたかった本の理想へ近づいて来ていると思う。もちろんその時々でどんどん変わって行くのが理想というものの厄介なところではあるけれど。
いまの執筆陣には、フライフィッシングをマニア的にやらない方が何人かいる。それぞれがそれぞれのオリジンな立ち位置で、世の中をじっくり見ている。その視線がフライフィッシング的かなと思うので、書いてもらっている。魚雷さんも四釜さんも、いまの『フライの雑誌』を奥深くしてくれている書き手の一人だ。
べつに相撲の雑誌に書いてる人が、全員相撲とりである必要はない。結果として雑誌の雰囲気がよければいい。
魚雷さんのいう「ひとつの窓」、なんかそれって、かっこいいじゃん、と思う。けれど同時に切実に思うのは、自分の「ひとつの窓」はおそらく、ものすごく狭くて、鉄格子がはまっている。外はおっかないから自分の窓にしがみついている。今いるタコツボは居心地いいかもしれない。海はずいぶん広いのにね、ということである。そのうちタコツボも経年劣化する。
およげたいやきくんは、あつくて狭くるしい鉄板を呼び出して、広い広い海へ泳ぎ出した。最初は気分よくももいろサンゴと交流していたものの、おそろしいサメにいじめられるわ、どんどんお腹は減るわでたいへんな苦労をした。あげく人間に喰われてそのはかない生涯を閉じた。うまそうにたいやきくんを喰ったのは釣り人のおじさんだった。釣り人とんでもない。
できれば世の中をのぞく窓は、大きくて柔らかくて透明でたくさんある方がいい。コンクリートでガチガチにかためられた窓のない刑務所よりも、好みの窓、風通しのいい窓、わいわいと面白そうな窓、いまは興味がなくてもなんとなく気になる窓、色とりどりの窓がはまっているアパートに暮らすほうが楽しそうだ。世の中をのぞくための窓のあれこれを用意するのが雑誌や町の書店の役割だ。
ネット時代だから、自分の好みを極度に掘り進んで周囲を最適化し、異質なものを拒否することもできる。でもそれって鉄板の上のたいやきの暮らしのようではないか。自分の窓枠に固執するのもいいが、半歩身を引けばそのぶん視野が広がる。
海には色んな出会いがある。釣り人に喰われるのを含めて、思いもよらない体験が待っている。
『Angling』創刊編集長の山田安紀子さんは、「釣りはハプニングが面白いのよ。」とおっしゃっていた。
5.3(火)、谷根千でやっていた「不忍ブックストリート」の一箱古本市へ行ってきた。




![『フライの雑誌』第106号|〈2015年9月12日発行〉| 大特集:身近で深いオイカワ/カワムツのフライフィッシング─フライロッドを持って、その辺の川へ。|オイカワとカワムツは日本のほとんどどこにでもいる魚だ。最近になって、オイカワとカワムツがとても美しく、その釣りは楽しく奥深いことを、熱く語るフライフィッシャーが増えている。今号ではオイカワとカワムツのフライフィッシングを、大まじめに真っ正面から取り上げる。この特集を読んだあなたは、フライロッドを持ってその辺の川へ、今すぐ釣りに行きたくなるでしょう。 新連載 本流の[パワー・ドライ] Power Dry Flyfishing ビッグドライ、ビッグフィッシュ|ニジマスものがたり](https://furainozasshi.com/wp-content/uploads/2015/09/106-cover-m-1.png)
大特集:身近で深いオイカワ/カワムツのフライフィッシング|オイカワとカワムツのフライフィッシングを、大まじめに真っ正面から取り上げました。この特集を読んだあなたは、フライロッドを持ってその辺の川へ、今すぐ釣りに行きたくなるでしょう。
新連載 本流の[パワー・ドライ] Power Dry Flyfishing ビッグドライ、ビッグフィッシュ|ニジマスものがたり
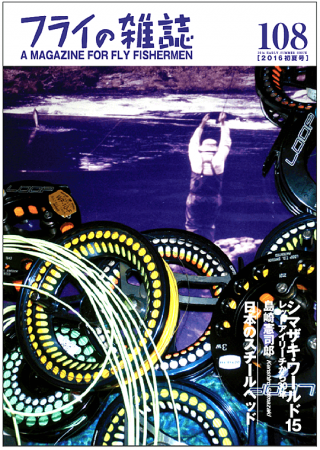

堀内正徳