そろそろマルタウグイの季節です。単行本『葛西善蔵と釣りがしたい』(フライの雑誌社2013年)より、「この雨が上がれば」を紹介します。
・・・・・・・・
毎年、三月下旬から四月上旬に東京へ多めの雨が降る。東京都を東西に流れ下る多摩川は、その時季に調布あたりで三〇センチほど水位が増える。実際に川へ立つと、三〇センチはかなりの増水だ。
増水が少し落ち着いた時、二子玉川から登戸にかけての多摩川中下流域に、マルタウグイの遡上のピークが来る。日本のウグイ属にはウグイ、ウケクチウグイ、マルタウグイ、エゾウグイの四種がある。名前は違うがどれも〝ウグイっぽい〟姿形をしている。その中でもっとも大型に成長するのがマルタウグイだ。
もともと多摩川には多くのマルタウグイが自然遡上していた。それが高度成長期の河川汚濁によりすっかり姿を消した。マルタウグイを呼び戻すため、下流域の川崎河川漁協が茨城県涸沼川から天然のマルタウグイを購入し、多摩川へ放流活動を始めたのが一九九〇年のこと。四〇センチ程度の抱卵した成魚を宿河原堰付近へ放流したという。放流されたマルタウグイは多摩川で産卵した。
五年目あたりから、目に見えて多摩川へマルタウグイが多く遡上してくるようになった。今では春、サクラの満開を待ちかねたように、多摩川の荒瀬では大量のマルタウグイが折り重なるようにして産卵行動をする。その光景は北海道の秋、カラフトマスやシロザケの産卵をほうふつとさせる。
海からのぼってきた親魚が川で産卵する。生まれた稚魚は海へ下り、何年かたって成魚となってまた川へ産卵に戻って来くる。遡河性の魚にとって当たり前のサイクルが、東京のど真ん中を流れる多摩川で、まさに当たり前に行われていることがどれだけ素晴らしいことか。
多摩川の野生マルタウグイの存在は、『フライの雑誌』第五四号(2001)の中本賢さんの連載記事で初めて世の中へ紹介され、多くの人が知るところとなった。マルタウグイは最大で七〇センチを超える。川では巨大魚といっていい。それが春のいっとき、すぐそこの多摩川にうじゃうじゃいて、バシャバシャと音を立てて産卵している。しかもフライフィッシングでよく釣れるとなれば、フライフィッシングのルネッサンスだといってはいいすぎか。
2002年からの5年間、わたしは京王多摩川駅近くの多摩川が見えるアパートに暮らしていた。二月末から五月末までのシーズン中は、毎日マルタウグイの遡上を追いかけて、多摩川沿いのサイクリングロードを走り回っていた。
背中には透明なプラスティックチューブをたすき掛けにしてある。中にはフライリールとフライまでセットされたフライロッドが入っている。格好はわるいが、腰までのウェーダー(長靴)を履いたまま自転車にまたがる。マルタウグイの群れを発見次第、背中からすらりと竿を抜き、川へ降りていってフライを投げる。
魚を釣りたいのはもちろんだが、いつごろどういう状況の時に、多摩川のどのあたりにマルタウグイが遡上してくるのかを、自分の経験として把握したかった。考えるより身体が先に動いていた。わたしは、〝多摩川でもっともたくさんマルタウグイをフライで釣っている男〟を自称していた。
多摩川でのマルタウグイのフライフィッシングは、ポイントの見定め方と釣り方のちょっとしたコツを知っていれば、一〇倍二〇倍に楽しみが増す。第六一号(2003)に「フレッシュ・マルタを狙え! 今年も多摩川はでかいマルタウグイで埋めつくされた」という記事がある。わたしが書いた。「フレッシュ・マルタ」とはフレッシュ・ラン(遡上したて)のマルタウグイという意味だ。そこではマルタウグイの釣り方について、具体的にくわしく解説した。
愛していたから。
釣り雑誌で初めて多摩川のマルタウグイのフライフィッシングを紹介したのはその前、第五七号(2002)の「海から来た魚」という記事だ。文と撮影は中沢孝編集長だ。なんとこの号は表紙までマルタウグイである。
本文グラビアの六〇センチオーバーの巨大なマルタウグイは、じつはわたしが釣った。それが証拠に、魚の傍らのフライロッドもリールもわたしのだ。ちょっと自慢だ。
中沢さんはそのときすでに深刻な病にかかっていて、入退院を繰り返していた。たまたま一時退院した際に、多摩川へマルタウグイを釣りに行った。土手にはサクラが満開だった。
中沢さんは角度を変え、光線を変え、露出を変えて、しつこく、本当にしつこく、わたしが釣ったマルタウグイを撮影していた。まだポジフィルムの時代だ。「海から来た魚」というタイトルにも、なんらかの含みがこめられているような気がしてならない。
釣り人は過去と未来を自在に行き来する。
このときの釣りも、つい先週の多摩川のようによみがえってくる。
(『葛西善蔵と釣りがしたい』84頁 〈釣り日記はいらない〉より)


















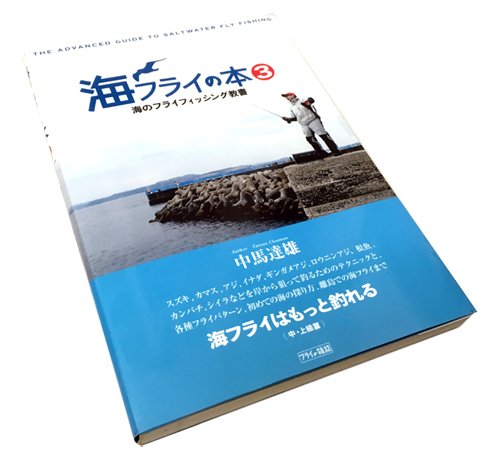

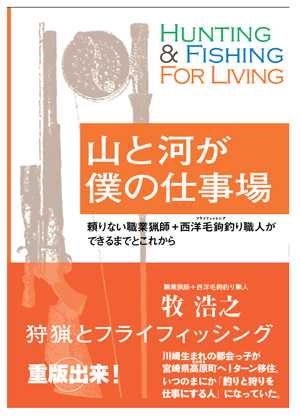
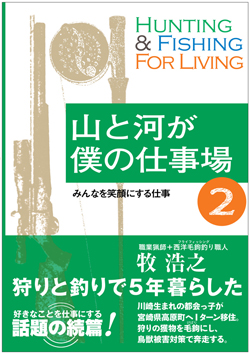



○天国の羽舟さんに|島崎憲司郎
○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在
『フライの雑誌』第113号
本体1,700円+税〈2017年11月30日発行〉
AMAZON
