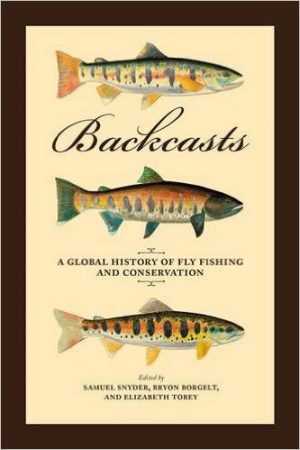
Univ of Chicago Press (2016/7/11)
Part Three: Native Trout and Globalization
11: A History of Angling, Fisheries Management, and Conservation in Japan
Masanori Horiuchi
(translated by Takayuki Shiraiwa)
・
・
・
日本のマス釣りを知っていますか
堀内正徳(東京都、日本)
[概要]
日本の川と湖にもマスが生息し、マス釣りが行われている。
本稿ではまず日本の川と湖の地質学的な特徴を概説し、再生産しているマスたちを紹介する。次いで、日本のマス釣りの社会学的な背景を明らかにするため、釣りにまつわる行政システムの説明を行う。
さらに、近代から現代に至るまでの、釣り人による河川環境保全の活動史を記録した上で、現在の日本のマス釣りをとりまく諸問題を、釣り人の視点から整理する。
マス釣りに関する水産研究の最新成果を紹介すると共に、若干の分析と考察を加え、日本のマス釣りを持続的に楽しむための提言を示したい。
・
・
・
第一章 日本の釣り場環境
アジア・モンスーン地帯に位置する日本は、周囲を海に囲まれた島国である。
1-1 国土が狭く人口が多い
国土は北から、北海道、本州、四国、九州、沖縄本島の5つの大きな島と、6800余りの小さな島々から成り立っている。面積は約37.8万km²で、ニュージーランドの約1.5倍。この国土に約1億3千万人が住んでいる。ニュージーランドの人口は約430万人である。
国土の南北端間の距離が約3000㎞と長いために、気候は亜寒帯気候から熱帯雨林気候と変化に富む。急峻な山が約7割を占める国土へ、世界平均の約2倍の雨が降る。※1
ほとんどの日本の川の水源は山岳地帯にあって距離が短い。自然湖は北海道と東日本に集中する。各地には人工的な貯水湖が多数点在している。
川は勾配が急であるため流量が急激に増大する。日本の伝統的治水工法は、水の勢いに逆らわないのが基本だったが、1868年の明治維新以降、河川は力で押えつける対象となった。河川改修とダム建設を進めてきた結果、水源から河口まで人間の手の入らない原始河川は、国土のほとんどから姿を消した。
1-2 箱庭のような川
都市圏の川を釣りのぼっていくと、釣り人は必ず堰やダムに行く手を遮られる。寸断された箱庭のような川底で自分が釣りをしていることに気づかされる。
都市周辺で、手つかずの自然にあふれた川でゆったり、のんびりと釣りを楽しむことは難しい。川には自然再生産したきれいな魚が少ない。釣りに行ったけれど、魚よりも釣り人の数の方が多かったとよく言われる。河川改修で痛めつけられているところに近年の集中豪雨などで、川床の安定しない河川が年々多くなっているように思う。
日本のマス釣り場環境の厳しさを理解していただけただろうか。紹介していてだんだんつらくなってきた。日本でマス釣りをするには、少々の困難にはへこたれない禅の修行が欠かせない。だから日本人の釣り人はほとんどが禅僧である(これは冗談です)。
次章では日本の渓流域に暮らしている魚たちについて知ってほしい。私たち日本のフライフィッシャーが愛してやまないサケ科魚類たちのことだ。きっと楽しい話になる。
◎
第二章 日本のサケ科魚類
日本の渓流域で生息数が多く、フライフィッシャーから広く愛されているサケ科魚類はヤマメ、アマゴ、イワナ、ニジマスの4種だ。
第1章で示したように、日本の川が育むことができるマス類の資源量は、釣り人の数に対して十分とは言えない。日本のほとんどの川と湖には漁業協同組合が設置されており、漁業権を持つ代わりに水産動植物を増殖する義務が法律で課せられている(本稿3-3参照)。
日本の内水面で、マス類の資源を減らさずに利用し続けるためには、人の手による増殖は不可欠だ。増殖方法の中で最も効率的だとして行政が漁協へ認めてきたのは、養殖魚の放流である。※2
マス類の移殖放流は、日本では長年にわたり行われてきた。その結果、生息地のかく乱が起こり、それぞれの川に固有の遺伝子を持った天然魚は少なくなってしまっている。※3
人工的な河川改変に加え、釣り人からの釣獲圧力、さらには移殖放流の影響により、日本のマスたちは追いつめられている。実際に日本の一般的な河川でマス釣りをしてみれば、誰もがたちどころに理解するはずだ。
2-1 ヤマメ、アマゴ
フライフィッシングの対象魚としてヤマメとアマゴは偉大な好敵手だ。夏でも20℃を越えない清冽な水に棲む彼女たちは(なぜか女性化したくなる)、警戒心が強く遊泳力はきわめて高い。ドライフライへ果敢にアタックしてくる。水中のフライへの反応もいい。とても美しく、淡白で上品な身は食べてもおいしい。
ヤマメ、アマゴともに、30センチを超えた個体は「尺もの」という尊称で呼ばれ、釣るのも格段に難しい。
2-2 イワナ
サケ科イワナ属。アメマス、ニッコウイワナ、ヤマトイワナ、ゴギの4亜種がいる。自然分布は北海道と本州だが、移殖放流により生息域は混然しており、交雑もみられる。
ヤマメ、アマゴよりも水温の低い水域に棲む。「ヤマメは瀬を釣れ、イワナは石を釣れ」という伝統的な教えがある。
マス類が生息する日本の山岳渓流では、水深が浅くて流れの速い瀬、流れの緩いトロ場、水深が深くて流れのよどんだ淵などが、連続して現れる。ヤマメ・アマゴは遊泳力が高く、流れが速くて開放的な場所を好む傾向があるために、瀬にいることが多い。イワナはふだんは岩などの障害物のかげに潜んで、じっとしていて、摂餌行動の時に姿を現す。ヤマメ・アマゴが女性なら、イワナはごつごつした男性のイメージだ。
イワナは気難しい性格だとされるが、喰いのたつ夕方などは、くるぶしほどの浅い水深の瀬へ、大胆に全身をさらけ出して盛んに水生昆虫を追う。こんな時はフライフィッシングの独壇場だ。
水生昆虫の他に陸生昆虫や他の魚類、小さなは虫類、両生類なども口にする。河川では最大で50センチ以上になる。
2-3 ニジマス
1877年、日本は米国から最初にニジマス卵の寄贈を受けた。1887年、日本政府は米国から輸入したニジマス卵を中禅寺湖と猪苗代湖へ移殖放流している。※4
「導入は1877年以降水産庁主導で正規に行なわれ、1980年代まで各地で盛んに放流されたが本州ではほとんど定着しなかった。現在も養殖・放流が盛んに行なわれている。全国的に養殖や管理釣り場で利用され、遊漁を目的として各地の河川や湖沼に導入されているが、今のところ北海道等の限られた地域でしか定着が確認されていない。」※5
20世紀初頭、日本は第一次世界大戦後の恐慌に加えて関東大震災の影響もあって、深刻な経済不況下にあった。内水面での食料生産を目的として、日本政府は魚類増殖の施策を行った。第二次世界大戦前だけで数十回にわたり、アメリカからニジマスをはじめ、ブルックトラウト、ブラウントラウトの発眼卵が移入され、各地の河川へ放流されている。※6
2005年施行の特定外来生物法([6-1]参照)において、ニジマスは「要注意外来生物」に指定された。しかしニジマスは内水面漁業の重要な養殖魚種である。2012年には約5147トンが内水面で養殖されている。※7 食用と遊漁のための種苗放流が主な用途だ。
区切った河川や人工的な池でニジマスを釣らせて、その場で食べさせるレジャー施設も多い。国策による最初の移入から130年以上を経たニジマスは、在来マス類と遜色ないほどに(あるいはもっと深く)、日本の一般市民の生活と結びついている。
北海道の川と湖ではニジマスが広範囲に自然再生産している。マス類の資源が乏しい日本において、多くの人は自然再生産したニジマスを有効に活用するべき資源だと考えている。大型の野生ニジマスを狙える釣り場として、北海道の川は世界的に注目されつつある。この点については「7-2」で述べる。
北海道の野生ニジマスを、北海道の貴重な観光資源にすべきだとする主張もある。その一方で、生物多様性を原理主義的にとらえる立場からは、ニジマスは日本の川にふさわしくないという意見も近年になって出てきている。この議論は現在進行中である。
◎
第三章 近代日本での川、魚、人の関係
約3千年前の内陸の遺跡から、ヒトに食べられた痕跡のある50センチほどの魚の骨が、原初の骨角バリと一緒に出土している。釣りを楽しんだ祖先の笑顔を思う。
3-1 川漁師の生きた時代
そもそも日本の渓流は、流域に暮らす住民が食糧として魚を獲る場だった。
現代の日本では考えられないことだが、かつて日本の渓流には、ヤマメ、アマゴ、イワナ釣りを職業とし、鮮魚を販売して生活を営んでいる専門の川漁師がいた。職漁には、よい魚が持続的に獲れる漁場とそれを現金化できる商いの場が必要だ。
自然の山と川の恵みが豊かだった当時の状況を以下に紹介する。(戸門秀雄. 2013『職漁師伝 渓流に生きた最後の名人たち』より引用) ※8
●17世紀、魚野川上流部秋山郷には、秋田県からマタギと呼ばれる山人がやってきて定着滞在し、職業としてイワナを釣っていた。1950年頃の秋山郷には25人のイワナ釣り師がいた。(67P.)
●長野県を流れる雑魚川には、20世紀初頭、専業のイワナ漁師の小屋が建てられ、1970年代になるまで受け継がれていた。(14P.)
●1935年頃、雑魚川のイワナは7、8匹で当時の日雇いの労賃に匹敵した。群馬県嬬恋の職漁師は年間に6~7000匹のヤマメを釣って地元の温泉地へ売った。(116P.)
1970年代に入ると、交通手段の発達により内陸部でも海産の鮮魚が入手できるようになった。川魚への需要も減った。1980年代に入り、日本の渓流域から専業の職漁師は姿を消した。
3-2 伝統漁法、テンカラ釣り
前掲書には職漁師が使った釣り道具の資料が多数掲載されている。職漁師の釣法はエサ釣りと毛バリ釣りが半々だったようだ。
渓流魚を対象とした日本式の伝統的毛バリ釣りを「テンカラ釣り」という。手返しのよさと質のいい魚を選んで釣れることで、職漁師も好んで使った。
3メートルほどののべ竿と糸、毛バリのシンプルなシステムが標準だ。毛バリは多くの場合、ハックルとボディだけで巻かれる。サイズはフライフックにして#18から#6ほどとまちまちだ。
毛バリはナチュラルドリフトしたり、逆引きしたり、深く沈めたり、水面で誘ったりと様々に扱われる。最近ではフライフィッシングのフライパターンを使う釣り人もいる。
規模が小さく流れの速い日本の渓流では、操作性の高いテンカラは有利とされる。現在もテンカラ釣りを楽しむ一般の釣り人は一定数いるものの、渓流釣り全体の人口では、エサ釣り、ルアー釣り、フライフィッシングの方がはるかに多い。
ごく近年になって、北米とヨーロッパの一部へ日本の伝統的なテンカラ釣りの手法が紹介されている。インターネット上の動画などで海外でのテンカラ釣りのシーンを観て、初めてテンカラ釣りの存在を知る日本の釣り人もいるようだ。
3-3 川と魚は誰のものか
近代以前の日本の民衆にとって、急峻な山村間の自由な移動は困難であった。人々の多くは水を得られる川沿いに定住して、ムラや部落と呼ばれる自足的な社会的共同体をつくり、協同的に農業を営んだ。渓流の魚は山村では貴重なタンパク源だった。川の生産力が乏しいことを知っている住民は、川を排他的に利用した。
「明治時代から戦後の漁業法ができるまで、河川では村や部落がよそ者には釣りをやらせなかった。釣らせる場合は風習として金をとっていた。権利はなかったが、あくまで風習としてそうなっていたんです。」(浜本幸生.1989年.『フライの雑誌』第11号)
海面および内水面での魚類資源維持を目的として、漁業法が1949年に公布された。管轄は水産庁である。第二次世界大戦後の漁業制度改革によって、旧漁業法(1910年施行)から切り替わった。
漁業法では魚類をレクリエーション資源としてではなく、漁業資源として位置づけている。そのため、レクリエーションとしての釣りを楽しみたい釣り人であっても、漁業をベースとする法律の枠組みに従わざるをえない。つまり、日本の釣りの基本法も漁業法ということになる。
日本の釣り場が法律上、釣り場ではなくて漁場であるということに、日本で釣りを楽しむ上で障害となる諸問題の要因の一つがある。漁業者以外の釣り人には、「遊びのために漁をする人々」=遊漁者という呼称を与えられている。水産庁が遊漁者を施策の対象として考えるようになったのは、2004年の「水産基本計画」以降のことだ。※9 (6-2参照)
内水面の漁業協同組合は法律で定められた一定の資格を有する有志が設立する。漁協が申請した漁業権は内水面漁場管理委員会での検討の後に、都道府県の知事が認可する。漁業権を持った時点で漁協の組合員は法律上は漁業者となる。
先に見たように、現在の日本の内水面渓流域には専業の漁業者はすでにいない。法律上は漁業者でも一般の釣り人と中身はなんら変わらない。ところが漁協が有する漁業権はとても大きな権利だ。
川で釣りをするには、漁業者と一般の釣り人は法律上は差別されないことになっている。日本において公共水面にいる魚は無主物であって誰のものでもない。ただし資源(魚)の管理者は漁業権を持つ漁協である。魚の増殖計画は漁協が定め、一般の釣り人の意見を反映させる義務はない。遊漁規則と呼ばれる釣り場利用のルールも漁協が定める。一般の釣り人はルール作りの議論から阻害されている。これらの矛盾は川を住民が排他的に利用していたムラの風習を引きずっているといえる。
漁業権のある川で釣りをするには、釣り人は都道府県が定める内水面漁業調整規則と、漁協が定める遊漁規則を守る義務がある。そして増殖行為の応分負担として、漁協へ遊漁料を払う。
内水面の漁業協同組合は、健全な漁場を維持管理する目的で、ダムや河川開発などに、漁業権を根拠にして反対することができる。しかし釣り人やカヌーイストなどは、漁協にとっての漁業権のような、河川環境の保全についての法律上の権利を持っていない。
ダムや堰の建設を阻止できる可能性のある唯一の法律上の権利は、漁業権だ。建設に同意した漁協へは漁業補償金の名目で開発者から金が支払われる。しかし繰り返しになるが、現在の日本の渓流域には専業の漁業者は一人もいない。そこには矛盾がある。
「ダム工事や河川改修が魚類に与える影響を貨幣に換算して、漁協へ補償金が支払われる。漁協は行政や建設会社などから交渉相手として社会的に認められている。今の漁業法のもとでは、漁協にがんばってもらわなくては遊漁の未来はない」(柳沢政之1990/『フライの雑誌』第12号)
水産庁は、内水面漁業とくに河川での漁業は、食糧を生産する第一次産業としては限界を迎えているととらえている。※10 桜井(1991)「河川漁業衰退過程の社会史」は、1950年代の高度成長期以降に、河川環境に関する漁協と遊漁者の発言力が増加したとしている。※11 水産庁は最近になって、釣りを地域振興に役立てるための施策を検討したいと表明してきている。※12
協同組合の活動理念は「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という相互扶助の精神にある。この精神が本来的に機能すれば、地域的特色をよく知る漁協による河川管理は、即応能力に富み、きめ細やかに行われるだろう。しかしながら必ずしもそうはなっていないのは、漁業法の規定が時代と乖離してしまっていること、漁協のパワーの減少、組合員の川への無関心が進んでいることなど、複合的な理由がある。
以上のように、内水面漁業協同組合に求められる社会的な存在意義は変化しつつある。実態を踏まえて、公布から60年以上がたった漁業法の見直しを求める声もある。
◎
第四章 環境保全に対する釣り人からのアプローチ
第二次世界大戦後、1950年代に始まる高度成長期と呼ばれる時代は、経済成長が政治と社会の最優先の課題となった。1960年、当時の自民党池田内閣は「国民所得倍増計画」を掲げた。道路や鉄道網の整備、工業地帯の建設などの名目で、国土の狭い日本の至るところで開発が行われた。政治と行政が主導して行う大型公共投資の象徴が、ダム開発や河川改修の土木工事だった。
1970年代初頭に自民党田中内閣が導入した政策は俗に「日本列島改造論」と呼ばれる。河川の護岸工事や人工的な流路変更、ダム開発、農業用の頭首工などを建設する際に、河川に生息する水生生物の存在が顧みられる発想はほとんどなかった。国土の乱開発による環境破壊により、釣り場から魚は急速に数を減らしていった。
自然環境は悪化する一方だった。釣り人はそれを目の当たりにした。経済成長と時期を同じくして、国民のあいだにレジャーブーム=釣りブームが起こった。よい釣りを楽しみつづけたいという心の求めに従って、乱開発に異議を呈する釣り人の声も、少しずつだが大きくなっていった。
1970年代から80年代の、釣り人による環境保全と釣り場作りのトピックを振り返る。
4-1 奥只見の魚を育てる会
本州新潟県にある奥只見ダム湖は、1960年の竣工当初は巨大イワナの宝庫だった。ところが釣り人が多く入るようになり、1970年中頃には産卵親魚の姿すら見えなくなった。その惨状を何とかしようと、1975年に「奥只見の魚を育てる会」が発足した。釣り好きで知られる高名な小説家の開高健が会長についた。
「只見川は(中略)今日までにおびただしい数の釣師を全国からひきよせました。その神話時代にはサケぐらいもあるイワナやニジマスがよく釣れたものでした。けれど、神話は数年もたたないうちに衰えてしまいました。釣師の数が急増し、みんながぶったくりで釣りまくった結果、いまではネコの朝飯のような小魚しか釣れなくなりましたし、数もひどい激減ぶりです。山も川も荒廃の一途をたどるわが国の顔がまざまざと見られます。」(開高健.1975年.「ごあいさつ」) ※13
「都会の釣り人、地元(民宿、釣り人)、地元役場が会員となり、生活や趣の異なる者たちが、奥只見の魚を育てるために、利害を超えて(ママ)集結した。会員数は75名」 ※14
会は漁業権を持つ魚沼漁協に対して、魚をふやすための方策を提案した。禁漁期の延長、禁漁区の設定、親魚と稚魚の放流などだ。結果、早くも翌々年の1977年には魚影の改善が見られたという。
湖にほど近い銀山平に、開高の文学碑が建っている。そこにはRoderick L. Haig-Brownの『A River Never Sleeps』を開高が日本語に訳した文言が刻まれている。
4-2 長良川河口堰反対運動
本州で唯一の本流に堰のない川として知られていた長良川に、河口堰の建設計画がもちあがったのは1960年代だ。工事開始前年の1987年、地元住民、都会の釣り人、カヌーイストなどが連携して河口堰反対運動へ立ち上がった。スローガンは「サツキマスを守ろう」。
反対運動の中心となった「長良川河口堰に反対する会」は、全国に横断的な組織をつくる、連続シンポジウムを開く、媒体へ意見広告を出す、国会議員へのロビー活動などの反対運動を展開した。1989年にはカヌー1000艇、3000名が参加した大規模な水上デモが行われた。
季刊誌『フライの雑誌』編集発行人の中沢孝(当時)は書いている。
〈1990年2月26日、東京で長良川河口堰建設反対デモが行われた。3000人が集まった。金銭的な利害関係から離れて「美しい川を、美しい魚を、美しい自然を」という声が基盤になっているデモは珍しいのではないか。金で買えないものだが、自分には尊いものなんだ! という気持ちが結集した。〉 ※15
工事は止まらず1994年に河口堰は完成するが、長良川河口堰反対運動は河川の自然破壊に対して、釣り人をはじめとしたリクリエーション利用者が異議を唱えることが、社会へ影響力を持ち得るという事実を残した。
4-3 多摩川を理想のつりぼりへ
1980年代後半、日本にフライフィッシング・ブームが起きた。人口一千万人の首都東京都では都心から2時間ほどの距離の、多摩川上流部が人気だった。狙いものはヤマメだ。核心部わずか6、7㎞へ、いい季節には数十人の釣り人が集中した。しかし、押し寄せる釣り人たちの要望に応えるだけの魚が川にはいなかった。
多摩川ではマスは自然再生産できない。放流で成り立つプット・アンド・テイク型の釣り場だ。しかし解禁日当日に漁協がバケツで放流する成魚は、待ちかまえているエサ釣りに、まもなく釣りきられてしまう。持ち帰り制限がないのだ。
1984年春、増え続けるルアー・フライの釣り人を嫌った多摩川を管轄する奥多摩漁協が、突然「ルアー・フライ禁止」を宣言した。
日本にルアーフィッシング、フライフィッシングの文化が輸入され、一般化したのは1970年代に入ってからのことだ。水産的な統計があるわけではないが、当時の日本の川釣りの人口比は、アユ釣りとエサ釣りが圧倒的だった。漁協の組合員は新しい釣りであるルアー・フライの釣り人が、「オラが川」に増えることを嫌った。[3-3]で見た漁協の排他性の現れだ。釣り人にも行政機関にも事前の相談のない、漁協の独断専行であった。
「ルアー・フライ禁止」は、猛反発を受けて撤回されたが、釣り人たちはそれを契機に現在自分たちがおかれている立場と、釣り場の管理体制へ自覚的になった。
フライフィッシャーが中心であった彼らは、法律を勉強し、「もっと気持ちのよいマス釣り」を実現するために、漁協と行政機関へみずからアプローチするようになった。釣り人は仲間を作り、情報を交換して互いに連携して行動するようになった。
大きな釣り堀である多摩川を、より理想に近い釣り堀にするためにどうすればいいか。釣り人グループは、奥多摩漁協と行政へいくつかのアイデアを提案した。「ブラウントラウトの試験放流」、「キャッチ・アンド・リリース区間設定」などだ。
フライフィッシングは欧米からの輸入文化であるから、一部の釣り人はフライフィッシングへの精神的なスタンス、ファッションをこぞって真似しようとした。キャッチ・アンド・リリースは欧米での先進的釣り場管理方式の象徴としてとらえられた。1984年当時、日本の渓流域、湖に、持ち帰りゼロのレギュレーションの釣り場は、ひとつもなかった。
日本の渓流魚のエサ釣りには、食料調達の意味合いが大きい。しかし日本では釣り場の環境と魚の数に対して、釣り人の数が多すぎる。主にフライフィッシングを楽しむ釣り人たちから、「キャッチ・アンド・リリース」を日本の川でも試してみたいという声が出てきたのは、当然のことだった。
◎
第五章 マス釣り人の全国ネットワーク、トラウト・フォーラム
奥多摩川における「キャッチ・アンド・リリース区間設定」の運動は、奥多摩漁協の同意を得ることができず、実現しなかった。多摩川での活動をきっかけに知り合った釣り人が中心となり、日本初のマス釣り人の全国組織─トラウト・フォーラムが生まれた。
5-1 トラウト・フォーラム発足
1990年6月に45人の発起人が集まり、〈トラウト・フォーラム設立趣意書〉を発表した。釣り人、水産研究者、行政経験者、釣り具メーカーなど、多様な社会的立場の人々が名前を連ねている。釣り人の属性はほとんどがフライフィッシャーだ。エサ釣り、ルアー釣りを排除したわけではないが、結果的に人口比率では最も少ないフライフィッシャーが、トラウト・フォーラムの中心となった。
フライフィッシングに重要な、健全な水生昆虫と魚のサイクルは、健全な河川環境があってこそ持続する。フライフィッシャーは、自分の楽しみのために自然を観察し、自然に寄り添う。日本の内水面の釣り人のなかで、フライフィッシャーは河川環境保全についての先進的な立場にあった。
同年9月にトラウト・フォーラムが発足した。専門的知識を持つ者の集まりである代表部会を東京に置いた。会員はそれぞれの活動テーマを掲げたプロジェクトを個別に立ち上げ、代表部会との情報交換の中から、問題解決の道筋を手探りした。
トラウト・フォーラムの活動は多岐にわたった。不当な遊漁規則の改訂への働きかけ、キャッチ・アンド・リリースの試行と影響調査、漁協の監視活動、公開セミナーの開催、プロジェクト単位での勉強会開催、釣り人が一日にどれだけのマスを釣っているかを探る「マス類釣獲実態調査」、水産庁養殖研究所の訪問、漁協・関係機関連絡先リスト作成など。
現在はあたりまえになっているコンビニエンスストアでの遊漁券販売も、トラウト・フォーラムの呼びかけが発端だ。トラウト・フォーラムのウェブサイトに活動年表が記録されている。
1992年3月、トラウト・フォーラム憲章が発表された。 ※16
「トラウト・フォーラムは、鱒釣りをスポーツとして行うものの集まりです。わたしたちは、このスポーツからより大きな喜びを得るため、ヤマメやイワナたちが棲む豊かな清流の復活と保存を願うものです。また、鱒釣りがスポーツとして社会に広く定着し、釣り人の声がより多く行政施策に反映されることを望むものです。そのために、わたしたちは釣り人のネットワークを広げ、釣り場づくりに必要な種々の科学的な調査を実施していきます。また、それらの実績をもとに河川漁協や行政に対し、鱒釣りの新時代を築くための、積極的な提言を行っていきたいと考えます。わたしたちは、このスポーツが自然の再生産システムとよりよく調和し、子どもたちの世代にも終わることなく、かけがえのない楽しみであり、活力の源泉であり統けるよう願うものです。そのために活動するのが、トラウト・フォーラムです。」
5-2 釣りの観点から河川環境を考える
トラウト・フォーラムの活動資金は会費と寄付でまかなわれた。最大時で会員数は約千人、予算規模は500万円を超えた。国内大手のルアー・フライメーカーから寄付金の申し出があったが、実際には寄付されなかったと事務局の木住野勇は後に述懐している。※17
日本の企業には公益に資するという風土が薄い。トラウト・フォーラムを自社利益のために利用しようとしたが、うまくいかないことが分かったために、寄付をとりやめたのではないかと考えられる。
会報誌は「トラウト・フォーラム・ジャーナル」。代表の時評的なコラム、会員からの活動レポート、水産研究者の小論考、法律に関する啓発コラムなどが載ったB5判の小冊子だ。約5000部が印刷され、会員と漁協、都道府県の水産課へ無料配布された。
1994年3月のトラウト・フォーラム主催のセミナー「日本の鱒釣りの新時代を探る」では、次のような意見が語られている。 ※18
「アメリカではフィッシュ&ゲーム局から釣り人へデータがフィードバックされてくる。日本の場合は釣り場管理にまつわる具体的なデータが専門家や行政からでてこない。河川問題は自然保護の問題に行き当たる。ところが我々の現在の活動規模ではそこまで打って出るパワーはない。今は釣りという接点から、ヤマメ、イワナが棲む河川を考えている。」(西山徹)
「川の理想型は時と場所によって変わる。…自分たちが望ましい釣り場をどんどん作ってしまえばいい。」(水口憲哉)
「日本は釣りの種類が異常に多い。まして釣り場に釣り人が集中して来る。交通整理がどうしても必要です。このまま放置して10年もたてば、処置なしの末期症状になってしまう。」(島崎憲司郎)
きもちのいいマス釣りを長く楽しむために、目の前に覆い被さっている大きな問題を何とか打破したいというパワーが、セミナー会場には、みなぎっていた。
西山が言っている通り、当時のトラウト・フォーラムには(後年においても)、自然保護や河川環境保全への問題意識はあったものの、具体的に自ら関わるだけの力はなかった。それでもそのころ釣り場の問題で困っている一般の釣り人には、トラウト・フォーラムが唯一の駆け込み寺であるかのように見えただろう。
トラウト・フォーラムの登場以前は、川の共同利用者として、行政や漁協との話し合いのテーブルに着くこと自体が、釣り人には許されていなかった。ものごとはひと息に変化しないが、あきらめなければふと気づくと大きな岩も少しずつ転がることを釣り人は学んでいった。
釣りはきわめて個人的な遊びだ。釣り場の好き嫌いを言い始めたら、建設的な議論にならない。本来働くべき漁協や行政に期待できない状況で、釣り人が汗と知恵を出し合い、力を合わせて最大公約数の快適な釣り場を作っていこうというのが、トラウト・フォーラムの活動だった。
5-3 キャッチ・アンド・リリースとその先へ
1996年7月にトラウト・フォーラムは新しい活動方針を発表した。〝マス類の自然再生産に向け、自然河川湖沼へキャッチ・アンド・リリース区間を設定することを目指す〟というものだ。
当時、トラウト・フォーラムで指導的役割を果たしていた人々は、しばしば北米大陸でのフライフィッシング体験を紹介した。その中で、たとえばイエローストーン国立公園でのノーキルのレギュレーションが、理想の釣り場の前提条件のように語られるケースがあった。よいマス釣り場=キャッチ・アンド・リリースの釣り場という誤解だ。
河川を区切って入場料を取って客を入れ、大量に放流したニジマスの成魚をエサ釣りで釣らせ、その場で食べさせる観光施設は日本全国にある。プット・アンド・テイクの究極といえるこの形態の釣り堀に慣れた釣り人は、釣り堀以外の河川でも釣った魚のすべてを持ち帰ることが当たり前になる。しかしもちろん、再生産力の乏しい日本の自然渓流で大量の釣り人がそのような釣りをすれば、マスはあっというまにいなくなる。
当時は、そもそも釣り場管理者である漁協も行政も、一般の渓流釣り場に持ち帰りのバッグリミットを定めていなかった。そんな状況では、解禁と同時に大挙してやってきて、何10匹、ときには何100匹とマスを持ち帰って殺してしまうエサ釣り師を制御する方法がない。
そこで、それまでの「持ち帰り自由」へのアンチテーゼとして「持ち帰りゼロ」を掲げるキャッチ・アンド・リリースの概念を啓発することが発案された。
現在であれば、キャッチ・アンド・リリース(ノーキル)が、釣り場マネジメントの一形態だというのは常識だ。尾数制限や体長制限、禁漁区や禁漁期間の設定など、釣獲圧を下げるための方策はたくさんある。しかし当時はそれらの議論がなされる共通認識がまだなかった。
本質的には、そもそも釣り場のキャパシティと魚の数に対して釣り人が多くなりすぎたのが、日本のマス釣り場での多くの問題の始まりだ。釣りを楽しむには、ほかの釣り人との距離は遠いほうがいい。また、キャッチ・アンド・リリースは禁漁一歩手前の処置であり、釣り人の行動を強く規制する。自由度の高い釣り場とは言えない。そういった本質論を置き去りにしたまま、キャッチ・アンド・リリースへの幻想が肥大化していった。
ゆたかな川=釣り場を守り育てるには、川が持っている自然再生産力を高め、保持するのが本筋である。しかしこの頃は、器の中身を分配するのに精一杯で、器そのものまで釣り人の手が回らなかった。
魚を殺さない釣り場をつくろうというトラウト・フォーラムの呼びかけには、全国から多くの反響があった。川にキャッチ・アンド・リリース区間を設定することはブームとなり、2001年で30カ所を超えた。しかしそれらのほとんどは、成魚を大量放流しリリースを義務づけた「つりぼり」だった。
それまで日本の水産研究は養殖が主体で、釣り場マネジメントに関する研究はごくわずかだった。トラウト・フォーラムのサポートメンバーでもあった加藤憲司が『ヤマメ・アマゴその生態と釣り 渓流マンのための生態学』(1990/つり人社)で発表した小さな図(※19)が、研究者から一般に発せられた唯一の釣り場マネジメント論であった。
よりよいマス釣り場を残すために、もっと奥深い議論と幅広い戦略が必要とされていた。魚がそこにいるだけでは、持続的なよい釣り場とは言えない。よい釣り場作りとは、川の自然環境の回復あるいは保全と不可欠のものだ。リリースはあくまで再生産のために産卵期まで魚を残すひとつの方法にすぎない。
こういった議論の末に、トラウト・フォーラムはキャッチ・アンド・リリース区間作りに関わる活動を縮小させていく。以降のトラウト・フォーラムは釣り場作りに役立つ情報を発信し、行政と交渉するセンター業務へと軸足を移す。
◎
第6章 釣り場と社会、転換の時代
6-1 生物多様性とブラックバス
1980年代に入ると、ルアー釣りによるブラックバス釣りが爆発的に流行した。若い世代の釣り人が大量に流入し、バス釣り関連産業が急伸長した。ため池やダム湖などの岸辺にはルアーロッドを持った釣り人があふれた。その状況を苦々しく受け止める層もあった。
1992年のリオ環境サミット以降、生物多様性の言葉がマスコミに登場する機会が多くなった。1990年代末から2000年代初頭の日本で、生物多様性は正しく理解されずに、外来種の排斥運動として具体化した。主に目の敵にされたのはブラックバスだった。
日本の在来魚が減少しているのは、ブラックバスに代表される外来魚による食害のせいだという主張が2000年前後に出現した。そのころの国内経済は、デフレーションに悩まされていた。不況への苛つきから派生したナショナリズムと、外来種の排斥運動とが結びついた。
2004年に特定外来生物法が新しく公布された。生物多様性を根本から破壊するのは自然破壊や開発行為であるが、この法律では規制していない。ブラックバスは自然破壊や開発への目くらましにされた形だ。生物多様性は本来の主旨ではなく、政治的な材料として利用された。
生物多様性を根本から破壊するのは自然破壊や開発行為であるが、この法律では規制していない。
島国の日本では、生物の移動は人々の暮らしに欠かせないものだ。主食のコメもユーラシア大陸伝来の植物である。特定外来生物法では、明治維新の時点で日本にいた生物を「在来種」とすると規定している。
しかし、移殖放流を重ねてきた日本の川や湖では、いつの時点のなにをもって〝本来の生物相〟と規定するかは難しい。漁業者は法律で決められた増殖義務を種苗放流で果たしてきたし、それを行政も認めてきた。放流種苗の質は問われなかった。
サケ科魚類の海外からの移入と国内移殖は、水産庁が推進してきた事業だ。全国各地の川と湖で多額の税金を投入して進められてきた。そういった過去の事実は、21世紀に入って登場した生物多様性の思想とはそぐわない。水産庁は苦慮しているが、今なおすり合せはできていない。
特定外来生物法により、特定外来生物を駆除する費用を国が補助するシステムが生まれた。以降、全国各地で「外来魚駆除釣り大会」が開かれた。
水辺の生物相が単純化する要因の根幹は、ダムや開発、河川改修など、自然環境の人工的な改変にある。本質の議論を置き去りにして、外来種がスケープゴートにされた。この構造を水口憲哉は「お粗末な政治と科学」と呼んだ。※20
人間の手が入って長い時間がたった二次的自然や、改変自然がほとんどを占める日本の国土では、生物多様性の概念を法律で一律に当てはめることはそぐわない。外来種だから殺せ、在来種だから守れという政策は、生物多様性保全から離れた排外主義やレイシズムであるといわざるを得ない。
魚ばかりではない。たとえば日本に入ってきてから何十年もたって子どもたちの遊び相手になっているアメリカザリガニのような小生物も、特定外来生物法ができたとたんに、駆除の対象となった。ドブのような川にも、アメリカザリガニが生息してくれていることへ、むしろ感謝するべきだと筆者は思う。
サンクチュアリ的なゾーン以外では、地域住民と利用者との話し合いの中で、身の回りにいてほしい生物相を考えていくことが現実的だろう。残されている良好な自然環境を保全すると同時に、自然資源の実態に即した活用方法が議論されるべきである。
「角を矯めて牛を殺す」ということわざがある。日本における一方的な外来種の排斥運動は、外見を整えるだけで、実際は牛の死期を早めるように筆者は思う。
6-2 水産庁連続勉強会と釣人専門官
[3-3]で見たように、水産庁は2004年の「水産基本計画」で、遊漁者を行政施策の対象として規定した。それに前後して、水産庁から一般の釣り人へ具体的にアプローチする動きが出てきた。そのひとつが、水産庁の有志が企画立案した「川と湖の釣りを考える連続勉強会」だ。
「川と湖の釣りを考える連続勉強会」は2003年から始まった。参加者は、川と湖の釣り人と漁協、学識者、マスコミなど横断的だった。内水面の釣りで何が問題か、これからどんな行動をすれば、快適な釣りを末永く続けられるのかの、ブレインストーミングの場だ。
議論のテーマには、内水面の釣りと生物多様性、外来魚問題への対応、釣りに関する施策と費用負担、外国制度の研究などがあがった。ほぼ月に一回ずつ、合計11回開催された。
2004年9月、島村宜伸農林水産大臣が、水産庁沿岸沖合課(当時)に、「釣人専門官」を創設した。日本で初めて、釣り人のために仕事をする国のポストが誕生した。「釣人専門官は、釣りその他の方法により遊漁をする者に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。」(省令より)。
初代の釣人専門官には「連続勉強会」の実質的な主宰者だった櫻井政和が着任した。
櫻井の口癖は「釣り人にパワーがほしい」だった。特定外来生物法の制定過程で釣り人の意見は無視された。時代の趨勢のなかで、釣り人には社会に認められる発言力と影響力が必要とされていた。
任期中、桜井は地域行政や釣り人団体、漁協などからの依頼を受けて、釣り人の社会学的な位置づけや、新しい時代における釣り人の役割について、全国を講演して啓発につとめた。
2006年、水産庁は一般の釣り人向けに「Recreational Fishing in JAPAN」というリーフレットを制作した。レクリエーショナル・フィッシングという単語を水産庁が公けに使用したのはこれが初めてだった。
6-3 渓流魚は量より質の時代へ
2008年春、水産庁は「渓流漁場の管理マニュアル」を発表した。制作には独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所(当時)に勤め、自身が渓流釣り師でもある中村智幸が関わった。中村は、養殖など水産技術の発展によって渓流魚の数が増えたことを認めつつ、その質を問題にした。
中村は渓流釣り場マネジメントの方法として以下を挙げた。
①放流、②濃密放流、③体長制限、④尾数制限、④キャッチ・アンド・リリース、⑤ルアー・フライ専用区、⑥ルアー専用区、⑦フライ専用区、⑧毛バリ専用区、⑨禁漁、⑩輪番禁漁、⑪人工産卵場、⑫人工産卵河川、⑬子ども専用区、婦人専用区など。 ※21
ヤマメ、アマゴ、イワナは秋、紅葉のころに産卵床を掘り、オスとメスがペアになって産卵する。川床が荒れて産卵床を掘れない河川で、人の手で川床を整え、流速を調整し、砂利を入れるなどして、親魚が産卵できる条件を作ってあげるのが⑪の人工産卵場だ。中村らが開発したばかりの新しい技術である。
6-4 放流から自然産卵の促進へ
筆者は同年頃から毎年、ヤマメ、イワナの人工産卵場の造成に関わっている。苦労して作っても必ず産卵してくれるとは限らないが、産卵場で野生魚が産卵している姿には神々しさを感じる。ふ化した稚魚の姿を見たときの喜びはことさらだ。
「産卵場の造成は、造成から稚魚の観察へと半年も続く自然体験教室になる。そのような体験を通して、子どもも大人も生命の神秘さを感じ、生き物をいつくしむ心をもつことができる」と中村は言っている。(中村智幸.2007年.『イワナをもっと増やしたい!』169P.)※22
「本当は人工の産卵場など造成せずにすのが理想です。〈魚が自然の産卵場を探して自由に移動し、行きたいところに行って、好きな場所で産卵する〉というのが本来の姿です。そのためには、産卵場への移動経路の確保が重要です。まず取り組むべきはダムの撤去や魚道の設置でしょう。」同170P ※23
「今の日本では、自然繁殖が見込める場所で、建設重機を使って人工産卵場を造成する、という非合理なことが行われないとも限りません。そのようなことが起きないように十分に注意を払って行く必要があります。」同172P ※24
渓流魚の人工産卵場造成には、川に入って石を運んだり砂利を掘ったりという、楽しい〝川遊び〟の側面もある。
各地で漁協、釣り人、住民、子どもたちが集まって産卵場をつくり、交流を持った。人間がなにもしなくとも自然再生産が期待される川では、あえて人工産卵場をつくる必要はないという啓発も行われた。 ※25
野生魚の産卵を手伝うことは、川に法律的権利を持たない釣り人が関われる、ささやかな河川環境の保全行為であるといえる。
2008年以降、水産庁は川と湖の魚の増殖について、稚魚放流、成魚放流、発眼卵放流といった種苗放流一辺倒から、天然魚・野生魚の自然産卵を助ける方向へと、舵を切ろうとしているように見える。より自然に近い形での増殖は、生物多様性のコンセプトにも合致している。最新のパンフレットでは、親魚を釣りきらずに残して自然産卵させる「親魚保護」や、産卵期に養殖親魚を放流して産卵させる「親魚放流」を提案している。 ※26
トラウト・フォーラムは、2008年3月、設立当初の目的を果たしたとして組織を解散した。今はメンバー各自が自主的な活動を続けている。埼玉県の会員らが荒川水系で行っているヤマメ、イワナの人工産卵場造りは10年近くも続いている。
◎
第7章 これからのマス釣り
マス釣り場をとりまく環境は、直近約20年で状況が激変した。これからの20年を見通す。
7-1 釣りブームは終った
近年、若い世代の釣りへの新規参入は、減少し続けている。高年齢者層は年々釣りから離れていくから、川と湖の釣り全体で考えると、釣り人口は減る一方だ。
漁協は高年齢化、弱体化している。旧態依然の漁業法はなお改正されていない。もっともこのような現状を踏まえると、漁協が釣り人と共同歩調さえとるならば、今あえて新しい行政システムを導入する必要性は薄いように思う。
釣りはスペースを占拠し、資源を消費する趣味だ。釣り人の頭数が減れば、釣りと釣り場に関する諸問題の多くは解消へと進む。しかし釣りを文化としてとらえると、釣り人が減りすぎるのも、日本の釣り文化の連続性、多様性と奥行きを阻害する。むずかしいところだ。
釣り具業界は、マーケットの縮小に伴い青息吐息だ。釣りで商売をしていながら、上質な釣り場環境の保全のために、釣り具業界が有効なアクションを起こしてこなかったのは残念なことだ。
内水面の漁協は高年齢化している。漁協経営は釣り人からの遊漁収入に頼っている。解散して漁業権を手離した漁協もある。
いまや釣り人と漁協は対立する相手ではない。「いい自然環境、いい釣り場を残したい」という目的のもとに、補完しあう仲間同士だ。河川環境を破壊するダムや河川改修などの開発行為に対して、漁協が釣り人と共に立ち向かう姿勢をとることが重要だ。
7-2 北海道は理想の釣り場か
北海道は、日本の中でもっともサケ科魚類の生息に適している場所のひとつである。
シロザケ、アメマス、ヒメマス、イトウ、オショロコマ、サクラマスという豊かな在来種を始め、移入種のニジマス、ブラウントラウト、ブルックトラウトも定着して親しまれている。国内外からの釣り観光客も多い。
北海道には、いまだ手つかずの自然が多く残されている。人口密度が低く川魚への需要も多くなかった北海道では、ほとんどの川と湖に漁業権が設定されていない。ライセンスが不要でコストも負担せずにマス釣りを楽しめる土地は、世界でもめずらしいだろう。
北海道ローカルの釣り雑誌『釣道楽』の坂田潤一編集長は、北海道での釣り場作りとは「釣り人の力でなんとかしようじゃなくて、なんにもしなくてもすむようにする」だと言っている。釣り場マネジメントの必要のない状態が理想だという主張だ。 ※27
北海道にも不安はある。北海道生物多様性保全条例が2013年に制定された。長年親しまれて貴重な水産資源であるニジマスを、北海道から駆除しようとする動きがあることが憂慮される。
生物多様性保全条例では、ニジマス、コイ、ギンブナ、サクラマス(アマゴ)、ナマズなど北海道に入って数十年以上たち、すでに市民生活に定着している魚を、国内移入種としてリストアップしている。
北海道はサケ科魚類を増殖するための、水産政策上の重要な拠点だ。生物多様性の観点から、水産的な経済行為をどのように位置づけていくのかの議論が必要だ。
国土交通省には北海道開発局という独自の機関がある。人の手が入りきらない領域の多い北海道では道路や林道、河川改修工事が盛んに行われている。ダム計画も多い。漁業協同組合がない川でダム建設計画が持ち上がった場合、地元住民、釣り人グループ、メディアが協同して対応し、開発者を話し合いのテーブルにつかせるところから始めざるを得ない。
7-3 20年後のマス釣りの未来は
日本のマス釣りの20年後の未来を考えてみる。
ダムや堰堤の建設、護岸工事により、水生生物の生息域の分断は進むだろう。ただしダム撤去の動きも増えているはずだ。
九州の球磨川では2013年から日本初のダム撤去工事が行われており、川の流れが生き返りつつある。ダムを作るのが建設費目当てのカネの論理だとすれば、同じくカネの論理で既存のダムの撤去が進む可能性もある。
20年後も、内水面の漁業協同組合は延命しているかもしれない。できれば河川利用者の合議の下、川や湖を共同運営する仕組みができているといいと個人的には考える。釣りは私的な趣味であり、個々人の生きがいだ。行政はできるだけ関わるべきではない。
特定外来生物法が残っているとしたら、釣りは年々きゅうくつなものになっているはずだ。釣りは管理された特定の水域で、アトラクション的に楽しむものという認識が進行しているだろう。スキーのゲレンデのように。
北海道の素晴らしいマス釣りは、今のままの状態であってほしいというのは、これは予測ではなくて願望だ。
国内の釣り具産業は、20年後にはほとんど死滅しているのではないか。種をまかず芽を育てずに資源を浪費するばかりの業界ならば、仕方ないことだ。
夢もある。
第4章でとりあげた多摩川は都市型河川の典型だ。40年ほど前までの多摩川下流域は生活排水と工業汚水の排水路にすぎず、生物の棲める環境ではなかった。
しかし下水道の普及で水質は回復し、魚道が設置されて、近年は遡河性のウグイやアユが再生産する川になった。
魚道が上流域まで完全に整備されて産卵場が確保できれば、サクラマスの復活も夢ではない。サクラマスの魚影が戻った近未来の多摩川を夢想する。そして多摩川が他の都市型河川の未来のモデルケースとなってほしい。
7-4 釣り人はあきらめない
最後にどうしても原発事故のことに触れざるを得ない。2011年3月に福島県にある東京電力株式会社福島第一原子力発電所が事故を起こした。事故は収束したと政府は言っているが、それが嘘だということを国民は知っているし、諸外国も信用していないだろう。
今なお、燃料プールには使用済みの核燃料が数千本も入ったままだ。メルトダウンした原子炉の核燃料をどうやってとりだし、どのように保管するかの目処もたっていない。
原発事故で、東日本の山も川も湖も、虫も鳥も魚たちも人間も、ひとしなみに放射能の雲に沈んだ。同じ国土に人間が立ち入ることができない川がある。渓流の美しいヤマメやイワナが、放射能で汚染される日が来ようとは、筆者はこれまで想像したこともなかった。
釣り人と住民、漁業協同組合、行政、水産研究者は長年いっしょになって、きれいな魚がたくさん泳いでいる美しい川、たのしい釣り場を作ろうとがんばってきた。たくさんの人がどれだけ真剣に関わってきたかを考えるほどに、悪い夢を見ているような気分だ。
放射能汚染された自然の前では、キャッチ・アンド・リリースも生物多様性も、河川環境の保全もヘッタクレもない。あまりにもきびしく、後戻りができない現実を前に無力感におそわれる。
しかし、だ。釣り人は本当に無力だろうか。釣り人は常に次のライズリングを探している。愛する山と川と自分たちの頭上に放射能が降りそそいだ現実の中でも、釣り人は希望を捨てないことはできる。
釣り人はしつこいオプティミストである。
日本の渓流は四季それぞれで美しい姿を見せる。今回紹介したマス類以外にも、フライフィッシングで遊べる愛らしい魚たちはたくさんいる。日本に来てくれたら筆者が案内します。
・・・・・・
引用文献:
1 MLIT, Water Resources in Japan in 2004 (MLIT, 2004).
2 Fisheries Agency, Manual for Fish Release in Freestone Rivers (pamphlet) (Fisheries Agency, 2008), http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/hatugannran.pdf.
3 Fisheries Agency, Manual for Zone Management at Fishing spots in Freestone Rivers (pamphlet) (Fisheries Agency, 2008), http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/zouning.pdf.
4 Takashi Nakazawa, 日本釣り場論24. Furai-no-Zasshi 47 (1999): 15.
5 MOE, Office for Alien Species Management of Wildlife Division of Nature Conservation Bureau http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/caution/detail_gyo.html#2.
6 Fisheries Agency, Manual for Fish Release in Freestone Rivers and Manual for Zone Management at Fishing spots in Freestone Rivers (material) (Fisheries Agency, 2008), http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/houryuu.pdf.
7 MAFF, The 2008 Sensus of Fisheries; Inland Water Fisheries, (MAFF: 2008). Furai-no-Zasshi 28 (1994).
8 Hideo Tomon, Tales of professional fishermen: last masters in Japanese rivers (Nosangyoson-Bunka-Kyokai, 2013), 14, 116.
9 Fisheries Agency, Master Plan for Fishery Industry (Fisheries Agency, 2002).
10 Fisheries Policies Planning Department of Fisheries Agency, Research for Fisheries Economy
No. 54, Research for Enviromental Changes around Inland Water Fishery and its Development 58 (Fisheries Agency, October 1995).
11 Masakazu Sakurai, Social History of the process of Declined River Fisheries (Master’s thesis, Graduate School of Tokyo Fishery University), 82.
12 Fisheries Agency, Research Report of the (Recreational) Fishing development system in USA, (Fisheries Agency, 2014), 1.
13 T. Kaiko, “Greeting”.1975.
14 The Society of Fish Reproduction in Okutadami website, http://www.trout-forum.jp/.
15 Takashi Nakazawa, 長良川河口堰建設反対デモが行われた. Furai-no-Zasshi 13 (1990): 146.
16 Trout Forum website, http://www.trout-forum.jp/.
17 Masanori Horiuchi. 日本釣り場論30. Furai-no-Zasshi 64, (2004): 56.
18 Takashi Nakazawa, [日本の鱒釣りの新時代を語る]で、何が語られたか. Furai-no-Zasshi 28, (1994): 50.
19 Kenji Kato, Ecology and fishing of Yamame and Amago—Ecology for freestone river anglers , 174; Management examples of fishing spots by categorizing natural fish and released fish(Tsuribito-sha, 1990).
20 Kenya Mizuguchi, Devil Fish Hunting; Why the Black Bass are killed (2005): 192.
21 Masanori Horiuchi. 日本釣り場論43. Furai-no-Zasshi 77 (2007).
22 Tomoyuki Nakamura, “Iwana o Motto Fuyashitai,” Furai-no-Zasshi-sha (2007): 169.
23 Nakamura, “Iwana o Motto Fuyashitai,” 170.
24 Ibid., 172.
25 Fisheries Agency, How to Create Artificial Spawning Grounds for Freestone River Fish, http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/jinko6.pdf.
26 Fisheries Agency, How to Breed Freestone River Fish (pamphlet), http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/keiryuu1.pdf.
27 Junichi Sakata. 日本のサケ・マス釣りの現状と問題. Furai-no-Zasshi 71(2005): 105.
・・・・・・
挿入写真キャプション
DSC_0911.JPG 北海道の河川で再生産したニジマス
yamame.jpg ヤマメ(山梨県桂川)
amago.jpg アマゴ(山梨県大門川)
rainbowtrout.jpg ニジマス(北海道尻別川)
flyfishing-in-Hokkaido.JPG 北海道尻別川水系でのニジマス釣り
IMGP3338.JPG ヤマメ、イワナの人工産卵場作り(埼玉県荒川)
IMGP2792.JPG アメマス(北海道湧別川)
DSC_8113.JPG 北海道の湖でのニジマスのフライフィッシング
DSC_8113.JPG テンカラ釣りによるイワナ釣りの風景(長野県遠山川)
DSC_0585.JPG 上流域でのフライフィッシングによるイワナ釣りの風景(長野県遠山川)
DSC_3984.JPG 初夏6月、新緑の中でのヤマメ釣りの風景(秋田県役内川)
IMG_2405.jpg 河川源流部でのオショロコマ釣り(北海道湧別川)
・・・・・・
“Many of us probably would be better fishermen if we did not spend so much time watching and waiting for the world to become perfect.”-Norman Maclean
Though Maclean writes of an age-old focus of all anglers—the day’s catch—he may as well be speaking to another, deeper accomplishment of the best fishermen and fisherwomen: the preservation of natural resources.
Backcasts celebrates this centuries-old confluence of fly fishing and conservation. However religious, however patiently spiritual the tying and casting of the fly may be, no angler wishes to wade into rivers of industrial runoff or cast into waters devoid of fish or full of invasive species like the Asian carp. So it comes as no surprise that those who fish have long played an active, foundational role in the preservation, management, and restoration of the world’s coldwater fisheries. With sections covering the history of fly fishing; the sport’s global evolution, from the rivers of South Africa to Japan; the journeys of both native and nonnative trout; and the work of conservation organizations such as the Federation of Fly Fishers and Trout Unlimited, Backcasts casts wide.
Highlighting the historical significance of outdoor recreation and sports to conservation in a collection important for fly anglers and scholars of fisheries ecology, conservation history, and environmental ethics, Backcasts explores both the problems anglers and their organizations face and how they might serve as models of conservation—in the individual trout streams, watersheds, and landscapes through which these waters flow.
CONTENTS
Foreword: Looking Downstream from A River
Jen Corrinne Brown
Acknowledgments
Introduction. A Historical View: Wading through the History of Angling’s Evolving Ethics
Samuel Snyder
Part One: Historical Perspectives1 Trout and Fly, Work and Play, in Medieval Europe
Richard C. Hoffmann
2 Piscatorial Protestants: Nineteenth-Century Angling and the New Christian Wilderness Ethic
Brent Lane
3 The Fly Fishing Engineer: George T. Dunbar, Jr., and the Conservation Ethic in Antebellum America
Greg O’Brien
Part Two: Geographies of Sport and Concern
4. Protecting a Northwest Icon: Fly Anglers and Their Efforts to Save Wild Steelhead
Jack Berryman
5 Conserving Ecology, Tradition, and History: Fly Fishing and Conservation in the Pocono and Catskill Mountains
Matthew Bruen
6 From Serpents to Fly Fishers: Changing Attitudes in Blackfeet Country toward Fish and Fishing
Ken Lokensgard
7 Thymallus tricolor: The Michigan Grayling
Bryon Borgelt
Part Three: Native Trout and Globalization
8 “For Every Tail Taken, We Shall Put Ten Back”: Fly Fishing and Salmonid Conservation in Finland
Mikko Saikku
9 Trout in South Africa: History, Economic Value, Environmental Impacts, and Management
Dean Impson
10 Holy Trout: New Zealand and South Africa
Malcolm Draper
11 A History of Angling, Fisheries Management, and Conservation in Japan
Masanori Horiuchi
Part Four: Ethics and Practices of Conservation
12 For the Health of Water, Fish, and People: Women, Angling, and Conservation
Gretel Van Wieren
13 Crying in the Wilderness: Roderick Haig-Brown, Conservation, and Environmental Justice
Arn Keeling
14 The Origin, Decline, and Resurgence of Conservation as a Guiding Principle in the Federation of Fly Fishers
Rick Williams
15 It Takes a River: Trout Unlimited and Coldwater Conservation
John Ross
Conclusion. What the Future Holds: Conservation Challenges and the Future of Fly Fishing
Jack Williams and Austin Williams
Epilogue
Chris Wood, CEO, Trout Unlimited
Appendix. Research Resources: A List of Libraries, Museums, and Collections Covering Sporting History, Especially Fly Fishing
Contributors
・・・・・・・
Backcasts
A GLOBAL HISTORY OF FLY FISHING AND CONSERVATION
EDITED BY SAMUEL SNYDER, BRYON BORGELT, AND ELIZABETH TOBEY
With a Foreword by Jen Corrinne Brown and Epilogue by Chris Wood
400 pages | 64 halftones | 6 x 9 | 2016
動画の中で『フライの雑誌』122号が紹介されています。
…
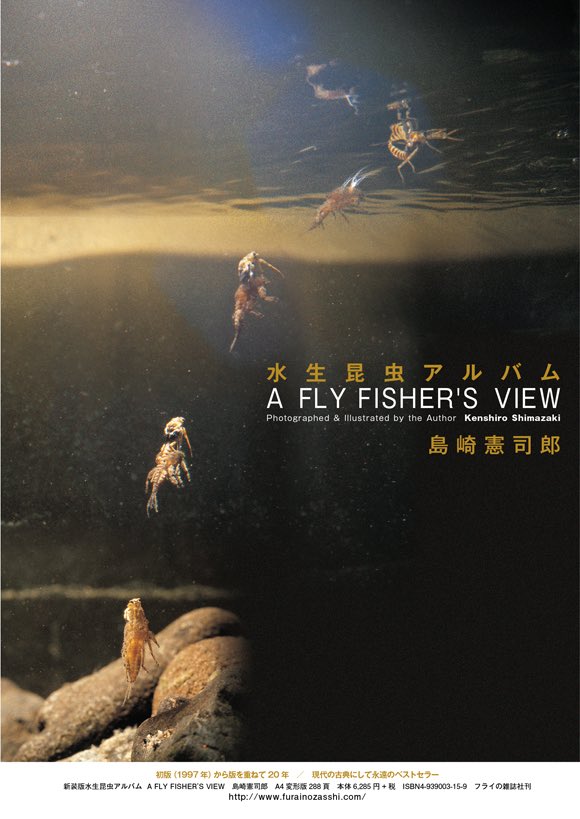

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。[フライの雑誌-直送便]新規お申し込みの方に〈フライの雑誌2023年カレンダー 小さい方〉を差し上げます。

単行本新刊
文壇に異色の新星!
「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)
『黄色いやづ 真柄慎一短編集』
真柄慎一 =著
装画 いましろたかし
解説 荻原魚雷
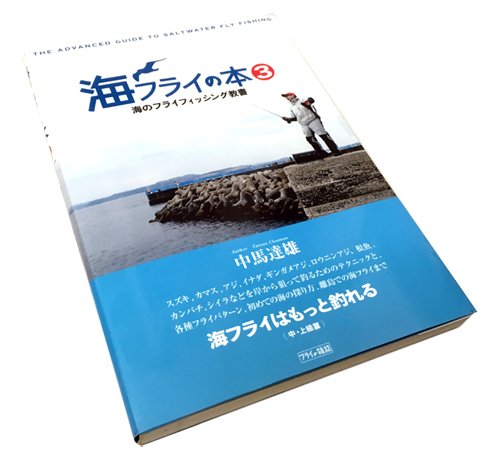

身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川

フライの雑誌 126(2022-23冬号)
特集◎よく釣れる隣人のシマザキフライズ2 Shimazaki Flies よく釣れて楽しいシマザキフライの魅力と実例がたっぷり。前回はあっという間に売り切れました。待望の第二弾!
CDCを無駄にしない万能フライ「アペタイザー」のタイイング|シマザキフライ・タイイング・ミーティング2022|世界初・廃番入り TMCフライフック 全カタログ|島崎憲司郎 TMCフックを語る|本人のシマザキフライズ 1987-1989
大平憲史|齋藤信広|沼田輝久|佐々木安彦|井上逸郎|黒石真宏|大木孝威
登場するシマザキフライズ
バックファイヤーダン クロスオーストリッチ ダブルツイスト・エクステンション マシュマロ・スタイル マシュマロ&ディア/マシュマロ&エルク アイカザイム シマザキ式フェザントテールニンフ ワイヤードアント アグリーニンフ シマザキSBガガンボA、B パピーリーチ ダイレクト・ホローボディ バイカラー・マシュマロカディス スタックサリー
シマザキフライとは、桐生市在住の島崎憲司郎さんのオリジナル・アイデアにもとづく、一連のフライ群のこと。拡張性が高く自由で“よく釣れる”フライとして世界中のフライフィッシャーから愛されています。未公開シマザキフライを含めた島崎憲司郎さんの集大成〈Shimazaki Flies〉プロジェクトが現在進行中です。
ちっちゃいフライリールが好きなんだ|フィリピンのフライフィッシング|マッキーズ・ロッドビルディング・マニュアル|「世界にここだけ 釣具博物館」OPEN|つるや釣具店ハンドクラフト展
発言! 芦ノ湖の見慣れぬボート ブラックバス憎しの不毛 福原毅|舟屋の町の夢 労働者協同組合による釣り場運営と子ども釣りクラブ|漁業権切り替えと釣り人意見|公共の水辺での釣りのマナー|アメリカ先住民、アイヌの資源利用と漁業制度に学ぶ|海を活かしてにぎやかに暮らす 三浦半島・松輪|理想の釣り場環境ってなんだろう 樋渡忠一|日本釣り場論 内水面における年少期の釣り経験|ヤマメ・アマゴの種苗放流の増殖効果|関東近郊・冬季ニジマス釣り場案内
6番ロッドで大物を。ブリ、カンパチ狙いのタックルとファイト|戦術としての逆ドリフト|阿寒川の見えないヒグマ 黒川朔太郎|ビルド・バイ・マッキー 堀内正徳|ナイフと職質 山崎晃司
水口憲哉|斉藤ユキオ|中馬達雄|川本勉|カブラー斉藤|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌-第125号|子供とフライフィッシング Flyfishing with kids.一緒に楽しむためのコツとお約束|特別企画◎シマザキワールド16 島崎憲司郎
座談会「みんなで語ろう、ゲーリー・ラフォンテーン」 そして〈シマザキフライズ〉へ

特集◉3、4、5月は春祭り 北海道から沖縄まで、毎年楽しみな春の釣りと、その時使うフライ ずっと春だったらいいのに!|『イワナをもっと増やしたい!』から15年 中村智幸さんインタビュー|島崎憲司郎さんのスタジオから|3、4、5月に欠かせない釣りと、その時使うフライパターン一挙掲載!
フライの雑誌』第124号

特集◎釣れるスウィング
シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!
『フライの雑誌』第123号
ISBN978-4-939003-87-5

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」(山﨑晃司著) ※ムーン・ベアとはツキノワグマのこと。

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)


中村智幸(著) 新書判 【重版出来】
